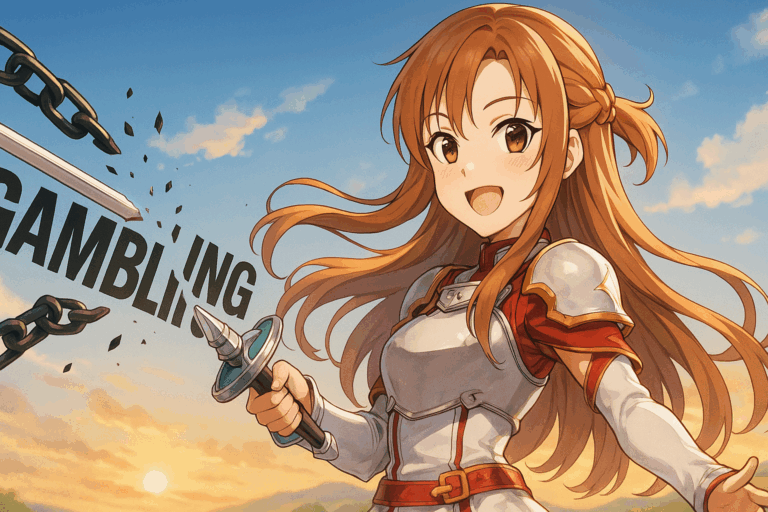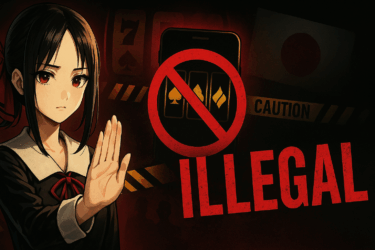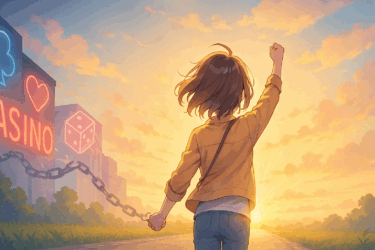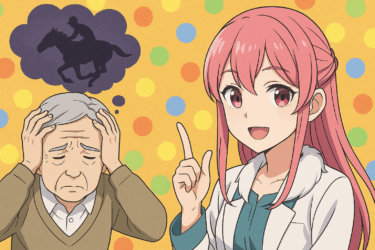ギャンブル依存症について、世間にはさまざまな誤解が存在します。もしかすると、あなた自身も「自分は意志が弱いからやめられないのでは?」「借金さえ返せば大丈夫?」などと悩んでいないでしょうか。こうした誤解は、本人の苦しみを深めたり、適切な支援を遠ざけてしまう原因にもなります。しかし、あなたが弱いわけではありません。正しい知識を持てば、この病気は決して克服できないものではないのです。 本記事では、ギャンブル依存症に関する代表的な7つの誤解について専門家の見解やデータを引用しながら解説していきます。
誤解1: 「依存症は意志が弱い人がなるもの?」
真実: ギャンブル依存症は本人の意志の強さ・弱さとは関係のない「脳の病気」であり、誰にでも起こり得る精神疾患です。 決して「怠け者」「意志が弱い人」だけが陥るものではありません。ギャンブルなどの依存症になると、脳内の報酬系や衝動のコントロール機能に変化が生じ、本人の努力や根性だけで克服することが極めて難しくなります。実際、アルコールや薬物の依存症と同様に医学的に認められた「脳の機能変化を伴う病気」であり、米国精神医学会の診断基準(DSM-5)でもギャンブル依存症(ギャンブル障害)は物質依存症と同じカテゴリに分類されています。
また、「依存症になるのはだらしない人だけ」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。むしろ現場の専門家の経験では、責任感が強く真面目で完璧主義な人ほどストレスをため込み、発散のためにギャンブルにのめり込んでしまうケースが多く見られます。そういった人は人一倍プレッシャーを感じやすく、「弱みを見せて人に頼るのは恥だ」という思いから孤独に抱え込んでしまいがちです。その結果、追い詰められた心を紛らわせる手段としてギャンブルに救いを求め、真面目な人ほど依存症に陥ってしまう paradox(逆説)も指摘されています。つまりギャンブル依存症は誰でもなり得る病気であり、性格の問題ではないのです。
まず押さえておきたいポイントは、「本人の意思の弱さではなく病気なのだ」という事実です。脳の病気である以上、意志の力だけで制御するのは困難であり、適切な治療と支援が必要になります。自分を責めたり「弱い人間だ」と卑下する必要はまったくありません。誤解による偏見は本人の苦しみを増し、助けを求めることを妨げてしまいます。「あなたは意志が弱いから依存症になるのではない」──これは専門家たちが口を揃えて強調するメッセージです。
理解度チェック:意志の弱さが原因?
▶正しいと思うもの すべて に✔︎を入れてください。
誤解2: 「借金を返せば治るのでは?」
真実: 借金問題の解消だけでギャンブル依存症が治るわけではありません。 確かに、ギャンブルによって生じる借金は深刻な問題ですが、それ自体は結果に過ぎず、根本原因である「ギャンブル行動のコントロール障害」を解決しなければ再び借金を繰り返してしまいます。
家族や周囲の人が陥りやすいのが、「借金さえ肩代わりしてあげれば本人も懲りてギャンブルをやめるだろう」という考えです。しかし専門家は、一時的に借金をゼロにしても問題は解決しないどころか、かえって長引かせると指摘します。実際、ギャンブルによる多額の借金に家族が驚き、みんなで立て替えて「二度としないでね」と約束させても再発するケースが非常に多いのです。周囲が尻ぬぐいをしてしまうと、本人は本当に追い詰められた「底つき体験」をしないまま問題をやり過ごせてしまいます。一時的に反省したように見えても、本質的な対策(治療や自助グループ参加など)を取らないままでは、しばらくしてギャンブルを再開してしまうのが典型です。専門用語でこれは「イネーブリング(enabling)」と呼ばれ、周囲の善意の援助が結果的に問題行動を可能にしてしまう現象です。
そのため、家族が借金の肩代わりをするのは厳禁です。消費者庁も「借金の肩代わりは本人の回復の機会を奪ってしまう」ので避けるよう注意喚起しています。借金問題の責任はあくまで本人に負わせることが、依存症克服のプロセスでは重要です。もちろん、だからといって見放すという意味ではありません。経済的な支援よりも、専門治療への橋渡しや精神的サポートといった形での支援が必要だということです。実際の治療では、借金整理は専門家(司法書士・弁護士など)と連携しつつ行いつつ、本人には経済的責任を自覚させる取り組みがとられます。借金がなくなれば依存症が「治る」わけではなく、借金は依存行動の結果にすぎません。大切なのは原因となっているギャンブル行動自体に働きかける治療を受けることです。
要するに、借金をゼロにすることがゴールではなく、「ギャンブルをやめ続けること」が真のゴールです。
理解度チェック:借金完済=完治?
▶正しいと思うもの すべて に✔︎を入れてください。
誤解3: 「ギャンブル依存症は完全に治らない不治の病なの?」
真実: 適切な治療とサポートにより、ギャンブル依存症から回復し健康的な生活を取り戻すことは充分に可能です。 確かに、ギャンブル依存症は再発リスクを抱える慢性疾患であり、一度治療に成功して長期間賭け事を断っていても、再び強い誘惑にさらされれば「スリップ(一時的な再飲酒・再賭博)」してしまう可能性はあります。このため専門家の中には「完治というより寛解(長期的な回復維持)」という言い方をする人もいます。しかし、これは決して「一生治らない」という意味ではありません。適切な治療プログラムの継続と支援によって、多くの当事者が日常生活を取り戻し社会復帰できているのも事実です。
実際、専門医療や自助グループに繋がりながらギャンブル衝動をコントロールし、健全な生活を送れる状態まで回復した人は大勢います。ある治療コラムでは「『治る』を“二度とギャンブルをしたくならないこと”と定義すれば難しいかもしれないが、『衝動をコントロールし健康的な生活を送れるようになること』と定義すれば、多くの人が回復を達成しています」と解説されています。この言葉が示す通り、ギャンブル依存症は克服不可能な病気ではありません。
重要なのは、「完璧にゼロになること」を焦るよりも「今日一日賭けない」生活を積み重ねていくことです。アルコール依存症のスローガンに「One Day At A Time(1日一日を大事に)」という言葉がありますが、ギャンブルでも同様で、まずは賭けない日常を積み重ねて脳と生活をリハビリしていけば、衝動は次第に弱まっていきます。実際、治療を続け1〜2年断ギャンブルを継続できれば相当安定し、再発率も下がることがわかっています。
なお、「完治しない=一生治療や自助グループに通い続けねばならない」という誤解もあるようですが、これも半分正しく半分誤りです。確かに再発予防のためには長期的なフォローが望ましいですが、それを負担と考える必要はありません。むしろ自助グループに定期的に参加し仲間と支え合うことが、回復者にとっては苦ではなく生活の一部・心の拠り所になっている場合も多いのです。そうした仲間のネットワークがあることで、たとえ一時的にスリップ(再賭博)してもすぐ立て直し、長期的に見れば「依存症からの回復状態」を維持していけます。
まとめると、ギャンブル依存症は適切な治療と支援によって「回復できる病気」です。本人の努力だけでなく周囲のサポートも含め、長い目で見たケアが必要ですが、希望を失う必要はまったくありません。
理解度チェック:回復は不可能?
▶正しいと思うもの すべて に✔︎を入れてください。
誤解4: 「自分は意志次第で今すぐギャンブルをやめられるはず」
真実: 「いつでも自分の意志でやめられる」というのは依存症特有の心理であり、残念ながら本人の意思だけで問題行動をコントロールすることは極めて難しいのが現実です。 多くの依存症当事者は、周囲から見れば明らかにコントロール不能な状態にあっても、「本気になれば今日からでもやめられる」「今はたまたまやめないだけ」と自分に言い聞かせています。しかし、これは脳が自分をだましている状態とも言えます。厚生労働省の資料でも「どこかで異常事態に気づきながら、『まだ大丈夫、いつでも止められる』と自分で自分をだましてしまう」のが依存症者の典型だと解説されています。
ギャンブル依存症に陥ると、理性では「やめなきゃ」と思っても、いざお金や機会があると衝動が勝ってしまうという自己コントロール障害の状態になります。例えば「今日はもう負けたからやめよう。明日から心を入れ替えよう」と思っても、翌日になると「やはり取り返したい」と考えて足が向いてしまう、といった具合です。「意志が弱い」とかではなく、病気によって脳の判断システムが変化してしまっているために起こる現象なのです。
むしろ依存症の典型症状の一つが「コントロール不能」であることを認識しましょう。DSM-5の診断基準においても、「減らそう・止めようと繰り返し努力しても成功しない」「問題が起きてもギャンブル行動を繰り返す」といった項目が挙げられています。つまり、「やめようと何度思ってもやめられない」のが依存症の症状そのものなのです。
本人が「やめようと思えばやめられる」と考えている間は、残念ながら本気で治療に取り組む動機が生まれにくいものです。このため、依存症はしばしば「否認の病」と呼ばれます。周囲から見れば明らかなのに本人は深刻さを認めず、「自分はまだ大丈夫」と否定してしまう傾向が強いからです。しかし実際には、本人の意思の力だけで問題行動を断ち切ることはできません。専門機関の治療や周囲のサポートを得ることが不可欠です。
もし「自分は意志が強いから大丈夫」「いつでもやめられる」と感じている方がいたら、少し立ち止まってみてください。本当に完全にコントロールできているなら、既に問題は起きていないはずです。「やめたいのにやめられない」と少しでも感じているなら、それは立派な症状であり、早めに専門家に相談するのが賢明です。
理解度チェック:意志で即断可能?
▶正しいと思うもの すべて に✔︎を入れてください。
誤解5: 「自分はまだ大丈夫。生活に支障が出ていないから平気?」
真実: ギャンブル依存症は進行性の疾患であり、「まだ大丈夫」と思っている段階で対処することが重要です。生活に大きな支障が出てからでは手遅れになる恐れがあります。 ギャンブル問題はある日突然破滅的な結果が訪れるわけではなく、少しずつ進行していきます。例えば初期の頃は「負けが込んでも仕事は続けているし、家族にもバレていない。借金だってまだ生活費を削れば返せる範囲だ」と思えるかもしれません。しかし、その状態が続くと借金が雪だるま式に増え、嘘や隠し事が増えて人間関係が悪化し、いずれ仕事や家族にも影響が及ぶのが典型的なパターンです。
実際、依存症の進行段階は概ね「初期→中期→末期」と分類されることがあります。初期段階では多少負けが込んでも「次は勝てる」と楽観視し、ギャンブルに費やす時間やお金が徐々に増えていきます。中期になると借金が始まり、家族や友人に嘘をついてギャンブルを続けるようになります。心の中では「このままではマズいかも…」という不安や自己嫌悪が芽生えますが、それでも「今回だけは…」と自分に言い訳しながら止められない状態に陥ります。末期(破滅段階)になると、借金が膨大になり返済不能に陥る、預貯金や資産も失う、職も失う、配偶者に愛想を尽かされる…といった深刻な事態に至ります。ここまで来てようやく本人も深刻さを認めるかもしれませんが、生活の破綻を経験してからのリカバリーは精神的・経済的にも非常に大変です。
重要なのは、「自分はまだ平気」と思っている段階で専門家の力を借りることです。ギャンブル依存症は、本人が問題を自覚して適切な対策を講じれば早期に回復できる可能性が高まる疾患です。厚生労働省も「他の病気と同様、早めの対応が回復への近道」と述べています。裏を返せば、「生活に影響が出てから」でないと相談してはいけない理由は全くありません。むしろ影響が大きく出る前に対処する方が、あなた自身の人生へのダメージを最小限に抑えられます。
「まだ大丈夫」という自己判断ほど危険なものはありません。 周囲から見れば既に「十分に危ない」状態でも、本人だけが楽観視しているケースはよくあります。例えば以下のような兆候が一つでもあれば黄信号です。
- 嘘や隠し事が増えている: ギャンブルのために使った金額や時間について家族や友人に嘘をついている。負けを誤魔化すために借金の理由を偽っている。
- 埋め合わせ行為がある: 「今回負けた分を取り戻せばやめよう」と考え、さらにギャンブルを続けている(いわゆる「追いかけ行為」)。
- やめるとイライラする: ギャンブルをしないでいると落ち着かずイライラするので、結局また手を出してしまう。
- 損失が膨らんできた: クレジットカードのリボ払い残高や消費者金融からの借入額が増えている。家賃や光熱費等に手が付くようになってきた。
- 周囲から指摘された: 家族や友人に「ギャンブルしすぎでは?」と心配されたり、何か様子が変だと指摘された。
これらは典型的なサインであり、たとえ現時点で表面的には生活が回っていても水面下では問題が進行している証拠です。
理解度チェック:まだ大丈夫?
▶正しいと思うもの すべて に✔︎を入れてください。
誤解6: 「ギャンブルぐらい、誰でも普通に楽しんでいるものじゃないの?」
真実: 確かに娯楽としてのギャンブルは世の中に広く存在しますが、「誰でも彼でもハマるもの」では決してありません。 多くの人は適度に楽しみ、コントロールしています。大事なのは「コントロールが効いているかどうか」であり、ここに依存症と趣味の決定的な違いがあります。
例えばパチンコや競馬などを娯楽として楽しむ人でも、ほとんどの人は時間やお金に自制心を働かせています。勝っても負けても「今日はここまで」と切り上げ、ギャンブル以外の生活(仕事や家族、他の趣味)とのバランスを保てているのです。こうした人にとってギャンブルは数ある娯楽の一つに過ぎず、人生の最優先事項ではありません。
一方で依存症状態にある人は、自分の意思ではそのコントロールができなくなっています。たとえ借金がかさんでも、健康を害しても、家族に愛想を尽かされても、それでもギャンブルを続けてしまう──それが依存症です。これは極端なケースのように思えるかもしれませんが、日本にも一定数存在します。実際、厚生労働省の研究班による2017年調査(生涯有病率)では、日本人の約3.6%がギャンブル依存症の疑いがあるとの推計が報告されました。また最新の全国調査(2021年)でも過去1年間にギャンブル問題が疑われる人は成人の2.2%(男性3.7%、女性0.7%)にのぼるとの結果が出ています。これを人口に当てはめると約220万人にもなります。決して少なくない数字ですが、裏を返せば約97〜98%の人は依存症ではないということでもあります。つまり「誰でもみんなギャンブルにのめり込んでいる」というわけではなく、 大半の人はコントロールしながら付き合えているのです。
「みんなやっているから大丈夫」「自分だけじゃないから平気」という考えは危険です。たとえ周囲にギャンブル好きな人が多くても、それぞれ状況は違います。他人が毎週パチンコに行っていても問題なく生活しているからといって、自分も同じようにできるとは限りません。大切なのは“他の人がどうか”ではなく“自分にとってコントロールできているか”です。
また、「娯楽としてのギャンブル」と「依存症としてのギャンブル」は質的に異なります。前者は人生を豊かにする娯楽の一部かもしれませんが、後者は人生を蝕む病的行動です。ギャンブル依存症はれっきとした精神疾患であり、趣味の範囲を逸脱しています。そのことを正しく認識すれば、「みんなやってるし平気だよね」と安易に考えることの危うさに気づけるはずです。
統計データが示す通り、実際に深刻なギャンブル問題に陥る人は一部です。しかし、一度依存症になってしまうと、ごく一部のケースを除き自然寛解(自力での回復)は難しいと言われます。
理解度チェック:みんな平気?
▶正しいと思うもの すべて に✔︎を入れてください。
誤解7: 「ギャンブル問題で専門機関に行くなんて恥ずかしい…」
真実: 依存症の治療を専門機関に相談するのは恥ずかしいどころか、早期回復のために最も賢明で勇気ある選択です。 病気になったとき医療機関にかかるのは何も恥ではありませんよね。ギャンブル依存症も同じ「病気」なのですから、適切な治療を受けることは恥じる必要のない当然の行動です。むしろ、専門家の力を借りず自力で何とかしようと無理を続ける方が、状況を悪化させてしまうリスクが高まります。
厚生労働省も「専門機関で正しい対処法を聞くことは恥ずかしいことではありません。自分たちだけで悩まず、専門の機関に相談しましょう」と公式に呼びかけています。事実、依存症治療の現場では「相談に来る勇気こそが回復への第一歩」とよく言われます。周囲に知られるのが恥ずかしい、人に頼るのはプライドが許さない、と感じるかもしれません。しかし、そうして相談を先延ばしにしている間にも病状は進行し、問題は深刻化してしまいます。
日本全国には、ギャンブル依存症の相談窓口や治療プログラムを提供している医療機関が多数あります。保健所や精神保健福祉センターでも依存症に関する相談を受け付けており、匿名で相談可能な窓口も整備されています。電話相談やオンライン相談を利用できる地域もあります。こうした専門サービスを利用することは何ら恥じることではなく、問題解決に向けた賢明な行動です。
また、相談や治療に訪れる人はあなただけではありません。同じ悩みを持つ当事者や家族が集まる自助グループ(ギャンブラーズ・アノニマス=GAや家族会=ギャマノンなど)では、皆が最初「恥ずかしい」「まさか自分が」と思いながらも、一歩踏み出して仲間と出会い回復に向かっています。そうした場所では恥や罪悪感ではなく共感と安心感を得られるはずです。むしろ「もっと早く専門機関につながっていれば…」という声も多く聞かれます。
繰り返しになりますが、依存症は病気です。恥ではありません。適切な治療やサポートを受けることは、あなたとあなたの大切な人の人生を取り戻すために欠かせないプロセスです。
理解度チェック:相談は恥?
▶正しいと思うもの すべて に✔︎を入れてください。
以上、ギャンブル依存症に関する代表的な誤解とその真実を見てきました。ギャンブル依存症は本人の人格の問題ではなく、正しい知識と適切な支援によって回復可能な病気です。誤解や偏見にとらわれる必要はありません。もしあなた自身やご家族がギャンブル問題に悩んでいるなら、どうか一人で抱え込まないでください。専門機関への相談は少しも恥ずかしいことではなく、それこそが回復への第一歩です。そして何より、「あなたは決して弱い人間ではない」ことを心に留めておいてください。適切な治療とサポートさえ受ければ、きっと元の健康な生活を取り戻せます。
依存症について正しく理解し、早めに対処することができれば怖れることはありません。専門家や同じ経験を持つ仲間は必ずあなたの力になってくれます。
この記事の総合理解度をチェック!
参考文献一覧
- ギャンブル依存症とはどんな病気?やめられない状態・特徴を解説 – うつ病ナビ(2023)
- 田辺等先生に「ギャンブル依存症」を訊く – 日本精神神経学会(2024年6月3日)
- 依存症になりやすい人はどんな人ですか? – ひだまりこころクリニック ブログ(2018/03/02更新)
- 依存症についてもっと知りたい方へ – 厚生労働省(依存症対策の啓発資料)
- 薬物依存症Q&A(家族向け資料 第5章) – 厚生労働省
- ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ – 消費者庁(注意喚起ページ)
- ギャンブル等依存症の正しい知識~予防と回復~ – ギャンブル依存症予防回復支援センター(資料)
- 「依存症」は誤解されている – Medical Tribune あなたの健康百科(2014)
- 厚生労働省 依存症対策 全国拠点機関リーフレット – 国立病院機構久里浜医療センター(2019)
- 病的ギャンブルに関する全国調査報告書 – 厚生労働省委託研究(2017)