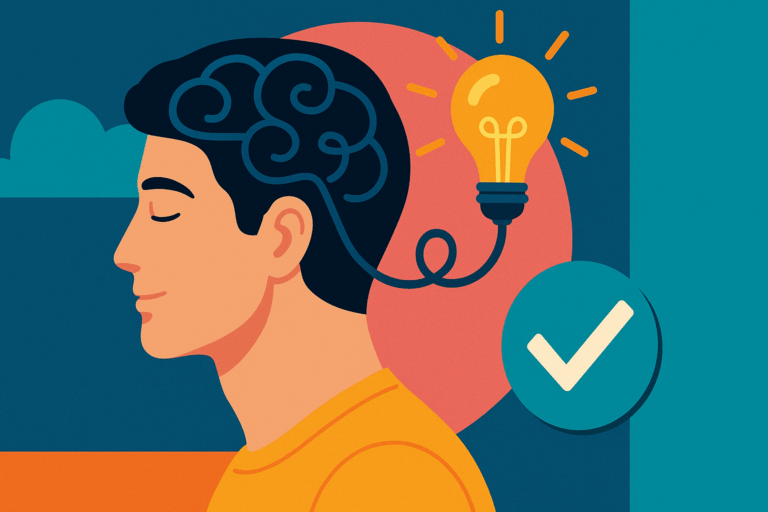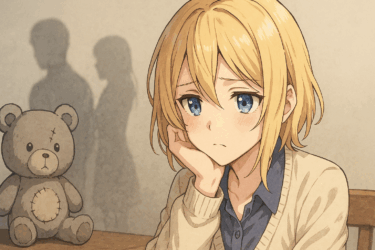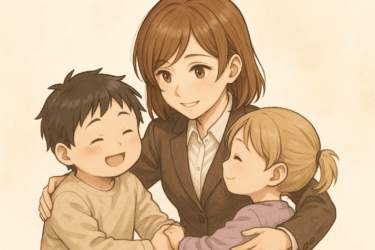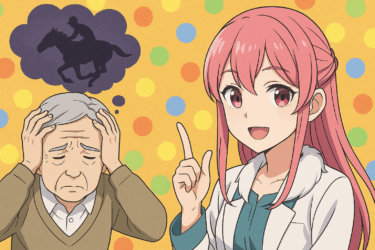依存症治療におけるカウンセリングとセラピーの役割
ギャンブル依存症(ギャンブル障害)は、本人の意思だけでは克服が難しい「心の病」です。単なる意志の弱さや性格の問題ではなく、脳の報酬系の変化により強烈な渇望( craving )が生じ、自分ではコントロールできなくなる状態を指します 。実際に、高額の借金や家族関係の悪化など深刻な問題が起きてもギャンブル行為をやめられずに続けてしまうのが特徴です 。このような状態から回復するには、専門的なカウンセリングやセラピーによる治療が極めて重要です。
ギャンブル依存症の治療では、心理療法(カウンセリング・セラピー)が中心的な役割を果たします。薬物依存症やアルコール依存症と同様、ギャンブル依存症でも認知行動療法(CBT)やグループ療法など有効性が科学的に確認された治療法が用いられています 。専門家のサポートを受けることで、依存行動を引き起こす考え方や感情に向き合い、対処スキルを身に付け、再発を防ぐことが可能になります。実際、ギャンブル依存症を自力で完全に克服できるケースは多くなく、専門家の治療・支援を受けることで回復できる可能性が大きく高まるとされています 。
また、カウンセリングを受けることは本人だけでなく家族の負担を軽減することにもつながります。依存症は本人以上に先に家族が問題に気づくことが多く、周囲だけで抱え込んでしまうケースも少なくありません 。専門機関につながれば、家族も含めた適切な対応策を教えてもらえます。早期の治療介入が日常生活の破綻を防ぐためにも重要であり 、問題を感じたら早めに相談することが勧められます。
ポイント: ギャンブル依存からの回復には、本人の意思に加えて専門的カウンセリングやセラピーの力が不可欠です。プロの支援によって、ギャンブルにとらわれた思考や行動パターンを変え、健康な生活を取り戻す手助けが得られます。一人で悩まず、専門家や支援団体に相談することが回復への第一歩となります。
主な心理療法の種類と特徴
ギャンブル依存症の治療に用いられるカウンセリングの種類にはさまざまなものがあります 。代表的な心理療法として、認知行動療法(CBT)、動機づけ面接法(MI)、家族療法、グループ療法(集団療法)などが挙げられます。それぞれアプローチや目的が異なり、対象者の状態に応じて使い分けられたり併用されたりします。以下では、主要な療法の特徴や効果、向いているケース、費用面などについて詳しく解説します。
認知行動療法(CBT) – ギャンブル依存に対する基本アプローチ
認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy: CBT)は、ギャンブル依存症の治療で最も頻繁に用いられる心理療法の一つです 。世界中の依存症治療の現場で効果が認められており、日本の専門治療施設でも広く取り入れられています 。CBTでは、人がギャンブルにのめり込んでしまう背景にある「認知(考え方)の歪み」と「行動パターン」に着目し、それらを修正することで依存行動を減らしていきます。
ギャンブル依存症の方は、例えば「今日は絶対に勝てるはずだ」「負けを取り戻せる」といった誤った信念にとらわれていたり、ストレス時にギャンブルで気分転換してしまうなどの習慣化した行動パターンがあります 。CBTではまず、そうした非現実的な思考(ギャンブルに関する誤信念)を本人が自覚できるよう支援します。具体的には、自分のギャンブルに関する考えを書き出し、それが統計的・論理的に妥当か検討するといった作業を行います。例えば「この機種なら当たる」という思い込みに対し、それを裏付ける根拠があるのか冷静に振り返る作業です。
また、トリガー(引き金)となる状況や感情を特定し、それに対する健全な対処法を学ぶのもCBTの重要な要素です 。ギャンブル欲求が生じる場面(給料日やパチンコ店の前を通るとき等)を把握し、その際に別の行動で切り抜けるコーピングスキルを練習します。深呼吸や誰かに電話する、一時的に所持金を減らす工夫など、衝動をかわす具体的な方法を身につけるのです。
さらに、問題解決技能の訓練や社会スキルのトレーニング、そして再発予防策も含まれます 。対人関係のストレスからギャンブルに走っていた人には断る練習をする、金銭管理の方法を学ぶ、再び衝動に駆られたときの対処計画をあらかじめ立てておく…といった具合です 。これらを包括的に練習することで、「ギャンブルをしなくてもストレスに対処できる」「ギャンブルに頼らなくても大丈夫だ」という自己効力感の回復を目指します 。
CBTは科学的エビデンスが豊富であり、研究でもギャンブル行動の明らかな減少効果が報告されています 。実践面では、通常週1回程度の個人セッションを数か月~1年以上継続します。治療効果を高めるために宿題(課題)が出されることも多く、患者自身が日常で対処法を試し、次回に振り返るという能動的な参加が求められます。
対象者: 本人が「何とかギャンブルをやめたい」「具体的な対処法を学びたい」という意思を持っている場合に特に適しています。強い動機がなくても、セラピストが動機づけをサポートしながら進めていきますが、ある程度治療に前向きである人の方が効果が出やすいでしょう。うつ病や不安症など併存症があって認知面の働きかけが難しい場合は、並行して薬物療法などで状態を整えつつ進めます。
効果・エビデンス: CBTにより認知の歪みが是正されると、ギャンブルへの衝動が減退し再発率が下がることが示されています 。国内外のガイドラインでも第一選択の治療法として位置付けられており 、多くの患者で経済的・心理社会的な回復が見られます。また集団認知行動療法の形で実施することで、後述するグループ療法の効果も取り入れつつ効率よく治療を行う試みも増えています 。
費用: CBTは医療機関やカウンセリングルームで提供されます。医療機関の外来精神科などで医師または公認心理師によって行われる場合、健康保険が適用されることが多く、自己負担は1回あたり数千円程度(3割負担の場合で約1,000~3,000円前後)になります※。一方、保険適用外のカウンセリング(自由診療)では、1時間あたり5,000~10,000円程度の料金設定が一般的です。ただし自治体の依存症相談施設では無料で相談・簡易的な支援を受けられる場合もあります。費用面が不安な場合は、後述する自立支援医療制度(精神通院医療)を利用できるか医療機関に確認すると良いでしょう。
※具体的な金額は治療機関や回数によって異なります。また自立支援医療制度を利用すれば自己負担額がさらに軽減されることがあります 。
動機づけ面接法(MI) – 変化への意欲を引き出すカウンセリング
動機づけ面接(Motivational Interviewing: MI)は、依存症治療の初期段階でよく用いられるカウンセリング手法です。「本人の中に眠る変わりたい気持ち」を引き出すことを目的としており、クライアント中心でありながらセラピストが戦略的に対話をリードしていきます 。ギャンブル依存症の場合、「本当はやめたほうがいいと分かっているが踏み切れない」「治療に来たものの迷いがある」という人は少なくありません。MIはそうしたアンビバレンス(やめたい気持ちと続けたい気持ちの両立)を解消し、治療への意欲を高めることを狙います 。
具体的には、セラピストが共感的に話を聴きつつ、適切に質問や要約を行っていきます。否定や説教はせず、本人が自ら「このままではいけない」「変わりたい」と気づくのをサポートする対話技法です。「ギャンブルでどんな良いことと悪いことがありましたか?」といった問いかけを通じて、本人自身にメリット・デメリットを整理させるなど、気づきを促すアプローチが特徴です。
MIの効果として、治療への参加率を高め、ギャンブル行動の減少につながることが研究で示されています 。比較的短期(数回)のセッションで大きな効果が現れるケースも多く、1回の面接でも動機づけに成功すればその後の治療成績が向上します。あるレビューでは、動機づけ面接を受けた問題ギャンブラーは、その後最大1年にわたってギャンブル頻度や費やす金額が有意に減少したとの報告があります 。
MIは「どんな人にも必ず良くなりたい気持ちは存在する」という前提に立ちます 。たとえ本人が「自分にはやめる気がない」と思っていても、実は内心では現在の状況を変えたいという希望が少なからずあるはずだと捉えます。そして適切な問いかけや要約、肯定的な返答によってその小さな動機を徐々に大きくしていきます 。この手法は抵抗感の強い患者にも有効で、「治療なんて無駄だ」と反発する気持ちさえも上手に利用しながら自己洞察を深め、行動変容につなげていきます 。
対象者: 治療への意欲が低かったり迷っていたりする人に適しています。例えば、「家族に連れて来られただけで自分は本気じゃない」というケースでも、MIを通じて本人の中から「変わりたい理由」を見いだせる可能性があります。また過去に治療に失敗した経験があり自信を喪失しているような場合にも、自尊心を傷つけずに前向きな気持ちを再燃させる助けとなります。
効果: MIによって治療継続率が向上し、ギャンブルによる浪費額や頻度が減少することが確認されています 。自己動機づけが高まるため、その後のCBTなど本格的治療へのスムーズな移行が期待できます。研究では、MIの効果は治療後半年~1年程度持続するともされ 、短期介入としては非常に有用です。また必要に応じて報酬付きプログラム(コンティンジェンシー・マネジメント)を組み合わせることで、初期の目標達成をさらに促す方法もあります 。例えば一定期間ギャンブルを断てたらご褒美を用意する、といった仕組みです。ただし日本ではこの方法を正式に導入している医療機関は多くありません。
費用: MI自体は比較的セッション回数が少なくて済むことが多いです。初回面接や動機づけカウンセリングとして数回行われる場合、医療保険適用内であれば1回あたり数百~数千円の負担で受けられます。民間のカウンセラーに依頼する場合も、短期間で終了するためトータルの費用負担は抑えられるでしょう。動機づけ面接は単独でも効果がありますが、しばしば他の療法への橋渡し役となるため、以降の治療(CBTや家族支援など)の費用も含めて計画を立てることが大切です。
家族療法 – 家族も巻き込んだ回復サポート
家族療法は、ギャンブル依存症の治療において家族やパートナーを含めたアプローチを取る心理療法です。ギャンブル問題は本人だけでなく家族全体の問題でもあります。借金の肩代わりや嘘による信頼関係の崩壊など、家庭内には大きなストレスが生じています。家族療法では、そうした家族システム全体に働きかけ、関係の改善と回復を目指します 。
具体的には、家族全員で話し合うセッションを行い、依存症への正しい理解を深めるとともに、お互いの気持ちを伝える場を設けます。セラピストはファシリテーターとして、家庭内で起きている問題のパターンに気づきを促します。例えば、本人がギャンブルをやめないことで家族がどんな感情を抱えているか、逆に家族の対応(小言を言う、借金を肩代わりするなど)が本人にどう影響しているか、といった点を整理していきます。
家族療法の大きな目的は、「混乱した家庭環境を落ち着かせ、支え合える関係を築くこと」です 。ギャンブル依存症の家庭では、しばしば怒りや失望の感情でコミュニケーションが断絶しがちです。家族療法では、家族が互いに率直に気持ちを話し、問題を家族みんなで解決していく姿勢を養います。これにより、家庭内の緊張状態が和らぎ、回復を後押しするサポート環境が整っていきます 。
また、家族側への教育的サポートも重要な要素です。依存症の家族は「もう二度としないで」と約束させて借金を返済してしまうなど、知らず知らずイネーブリング(enabling:問題行動を結果的に助長する関わり)をしてしまうことがあります 。家族療法の場で専門家から「尻ぬぐいをしない勇気」の大切さや、境界線の引き方を学ぶことで、家族自身も健康的な対応が取れるようになります 。例えば、金銭管理のルールを決めたり、嘘を見抜いたときの対処法を相談したりします。
効果: 家族療法により、家族からの支援が適切に機能するようになると、患者の治療継続と再発防止に良い影響を与えるとされています 。家族の協力を得られた患者は孤独感が減り、自己変革へのコミットメントが高まる傾向があります 。実際、家族が治療に関与した方がギャンブル断念率が上がるとの報告もあり、家族療法は依存症治療の有効な一手段と考えられています 。
ただし、日本では家族療法を実施できる専門家の数がまだ限られているとの指摘もあります 。また本人が治療に来ていない段階で、家族だけが相談に訪れるケースもあります。そのような場合でも、家族教室や家族向けプログラムを提供している施設も増えてきており、家族が情報やサポートを得られる場が用意されています。
対象者: 家族療法は、本人の回復に家族も積極的に関わりたい場合に適しています。特に夫婦間の問題が大きいケースや、親子関係が悪化しているケースでは、有効なアプローチとなります。また、本人が治療に消極的な場合でも、まず家族だけで相談に乗り、家族経由で本人の動機づけを図ることもあります。未成年や若年者のギャンブル問題では、親を交えた家族面接がほぼ必須となるでしょう。
費用: 家族療法は通常カウンセリング1回分の料金で家族単位の面接を行います。医療機関で行われる場合、1回の家族面接に対し保険点数が設定されていることもあります(家族療法加算など)。公的機関の家族教室や家族会は基本無料です。民間カウンセラーによる家族カウンセリングは1時間1〜2万円程度の場合もありますが、回数はそれほど多くならない傾向です。費用面でも家族全員で1回受ければよいため、一人ずつ個別に通うよりは効率的とも言えます。
補足: 家族自身が同じ境遇の家族と情報交換する家族向け自助グループ(後述)も並行して利用すると効果的です。例えばギャマノン(ギャンブラーズ・アノニマスの家族版)などのグループでは、家族療法で学んだ対応を継続する上で仲間から励ましを得られるでしょう。
グループ療法(集団療法) – 仲間と共に取り組む治療
グループ療法(集団精神療法)は、同じ問題を持つ複数の患者がグループで行うカウンセリングです。専門のセラピストまたは医師の指導の下、数人から十数人のグループで定期的に集まり、お互いの経験を共有したり、テーマに沿った討議や心理教育を行ったりします。ギャンブル依存症の治療でもグループ療法は重要な役割を果たしており、依存症専門病院やリハビリ施設では標準的なプログラムに含まれていることが多いです 。
グループ療法の最大の特徴は、「仲間から学ぶ力」です。他のメンバーが体験談を語るのを聞いて、自分では気づかなかった問題点に気づいたり、新たな対処法のヒントを得たりできます 。例えば「給料日が危ない」という話に共感し、自分も給料日に通帳を預けてみようと思うかもしれません。また、自分が発言し他者に受け入れられることで孤独感が和らぎ、安心感を得られます 。依存症の方は「自分はダメな人間だ」と自己評価が低くなりがちですが、仲間と支え合うことで自己肯定感が少しずつ回復していきます。
グループ療法の形式には、集団認知行動療法(複数人でCBTのワークを行う)やミーティング形式(フリーテーマで体験談を話す)など様々あります。共通するのは相互支援と集団力動の活用です。メンバー同士が質問し合ったりフィードバックを送る中で、個人療法では得られない多面的な視点が養われます。「自分だけじゃない」と思える安心感は、依存症克服において非常に重要です。
効果: 研究では、グループ療法に参加することで治療効果が増強されることが示唆されています 。個人のCBTに加えてグループでの話し合いに参加すると、より深い内省が促され、考え方や生き方を改めるきっかけが増えるためと考えられています 。またグループでの絆ができると、治療終了後も自主的に連絡を取り合ったり、自助グループに一緒に通ったりするなど、長期的なサポートネットワークにつながる場合もあります。孤立を防ぎ、再発の兆しがあれば仲間が気づいて声をかけてくれるといった効果も期待できます。
対象者: 基本的にすべてのギャンブル依存症患者に有益ですが、特に「自分だけがこんな思いをしているのではないか」と孤独を感じている人や、他人の意見に耳を傾けることで学べる人に適しています。他者と話すことに強い不安がある場合は、最初は抵抗を感じるかもしれませんが、進行役がしっかりフォローするので徐々に慣れていくことが多いです。また、グループ内で刺激を受けすぎて逆にギャンブル欲求が喚起されるのではという心配もありますが、その点もファシリテーターが管理し、安全な場作りが行われます。
費用: グループ療法は一人当たりのコストが比較的低いのが利点です。医療機関のデイケアや依存症リハビリプログラム内で提供される場合、保険適用となり月額定額の自己負担(自立支援医療利用で月1万円程度上限など)で何度でも参加できるケースもあります。病院によっては外来グループミーティングを1回数百円程度で開催しているところもあります。自助グループ(後述するGAなど)は基本無料(任意の寄付のみ)なので、金銭的負担なく仲間と話し合う場を持つことができます。グループ療法自体は利益を追求しない治療的集まりなので、費用面で参加を諦める必要は低いでしょう。
自助グループとの違い: グループ療法は専門家主導で治療的目標に沿って進められるフォーマルな治療ですが、後述する自助グループ(例:ギャンブラーズ・アノニマス)も同じ「仲間の力」を活用する点で共通しています。多くの場合、治療プログラム修了後も継続的に自助グループに参加することが推奨されます 。したがって治療段階ではグループ療法、維持段階では自助グループという形で両者を連続的に利用することも有効です。
その他のアプローチ(マインドフルネス・薬物療法など)
上記以外にも、ギャンブル依存症の改善に使われるアプローチはいくつかあります。例えばマインドフルネス療法は近年注目されている手法で、瞑想などを通じて衝動や欲求を客観視し、受け流す力を養うものです 。ストレスや感情の波に飲まれにくくなるため、ギャンブルへの強い衝動をやり過ごすスキルとして有用です。またソーシャルスキルトレーニング(SST)は、対人関係のストレスから逃避する目的でギャンブルに走っていた人などに対し、断り方や主張の仕方といった社会生活技能を向上させるプログラムです 。これも依存症治療の補助として提供されることがあります。
日本独自のものとしては、内観療法が挙げられます 。内観療法は自分が周囲から受けた恩やかけた迷惑を内省する心理療法で、もともとアルコール依存症の入院治療などで取り入れられてきました。ギャンブル依存症についても内観を行うことで、自分の行動が家族に与えた影響などを深く見つめ直し、更生の決意を固める効果が期待できます。実際、アルコールや薬物と同様にギャンブル依存症にも内観療法は有効であるとの指摘があります 。ただし、かなり集中的かつ専門的なプログラムになるため、実施している施設は限られます。
行動療法的アプローチも試みられています。例えば曝露療法は、実際に賭けをしないままパチンコ店に入る訓練や、ギャンブル場面を想像上で体験するイメージ曝露(系統的脱感作)によって、ギャンブル欲求に慣れていく方法です 。強い欲求や不安も、曝露を繰り返すと次第に弱まる性質があるため、衝動に打ち克つ訓練になります 。この手法はまだ研究段階ですが、再発予防プランに組み込むことで結果が改善したという報告もあります 。また代替行動の強化(ギャンブル以外の趣味や楽しみを見つけてそれに集中する)も行動療法的には重要な戦略です 。
一方、薬物療法についても触れておきましょう。現時点でギャンブル依存症に対する決定的な薬は存在しませんが、症状に応じて抗うつ薬や気分安定薬、衝動抑制を狙った薬剤が試みられることがあります 。たとえばSSRI系抗うつ薬(例:エスシタロプラム)や、アルコール依存症治療薬として使われるナルトレキソン(オピオイド受容体拮抗薬)などがギャンブル衝動を和らげる可能性が指摘されています 。しかし米国FDAが承認した薬はまだなく、エビデンスは限定的です 。日本でも臨床研究は進んでいますが、「薬でギャンブル欲求をゼロにする」ような劇的な効果は期待できないのが現状です 。したがって薬物療法はあくまで補助的に、不安や抑うつの治療、衝動性の緩和などを目的に用いられます。
総じて、ギャンブル依存症の治療は複数のアプローチを組み合わせて行われることが多いです 。認知行動療法で思考と行動を修正しつつ、必要に応じて家族療法で環境調整を図り、グループ療法で仲間の支えを得る——こうした総合的な支援により、依存症からの回復率が高まります 。患者一人ひとり状況が異なるため、専門家と相談しながら自分に合った治療プランを見つけることが大切です。
治療法の選び方:自分に合ったアプローチを見つける
様々なカウンセリングやセラピーがある中で、自分や家族にはどの治療法が適切なのか悩むことも多いでしょう。ここでは、治療法を選ぶ際に考慮すべきポイントを解説します。症状の重症度や生活環境、本人の性格や意向によって、最適な組み合わせは異なりますが、基本的な判断材料を知っておくことで方向性が見えてきます。
重症度の見極めと治療環境の選択(通院 vs 入院)
まず重要なのはギャンブル依存症の重症度です。例えば、「少しお金を持つとすぐギャンブルに行ってしまう」「通院治療中でも衝動が抑えられず悪化してしまう」という重度のケースでは、入院治療も検討されます 。入院治療は一定期間ギャンブルから隔離された環境で集中的に治療を行うもので、強制力と安心感があります。金銭や時間の管理も医療スタッフが行うため、自宅ではコントロール困難だった人でも賭け事から離れることができます。特に、自殺念慮がある場合や家庭環境が不安定で通院継続が難しい場合には入院が安全策となります。
一方、そこまで重症でなかったり本人が比較的コントロールできている場合、外来通院での治療が一般的です。通院治療の利点は、普段の生活を維持しながら治療を受けられることです。仕事を続けたり家庭での役割を果たしながら、週に1~2回クリニックに通ってカウンセリングを受けることが可能です。多くの依存症治療専門機関では、初診後にプランを立て、概ね半年~2年ほど通院を継続するよう勧めています 。途中で調子が良くなっても、油断せず一定期間フォローアップすることが再発防止の鍵です。
入院治療のメリット・デメリット: 専門病院に入院すれば24時間体制で見守りがあり、個人・集団両面から集中的に治療が受けられます。特に依存行為を絶つ最初の数週間~数ヶ月は、誘惑の多い外の環境より入院環境の方が成功しやすいと言えます。また同じ病棟に依存症仲間がいることで強い共感と刺激を受けられる利点もあります。しかし、長期入院は職場や学校を休む必要があり経済的・社会的ハードルが高い面もあります。費用は保険適用でも自己負担が1ヶ月数万円以上になることもありますし、そもそも入院治療を行っている施設が少ない(各地域に限られる)という現状もあります 。
通院治療のメリット・デメリット: 通院治療は日常生活を送りながら進められるため、社会的なブランクを作りません。費用負担も入院に比べれば抑えられます。ただし、日常生活の中にギャンブルの誘惑が残る状態で治療に取り組むことになるため、高い自己管理能力が求められます。治療の合間に再度パチンコ店に行ってしまうリスクと常に隣り合わせです。このため、通院の場合は家族の協力や環境調整が重要になります。例えば家族に金銭管理を任せる、一人きりの時間を減らす、通勤経路を変えるなどの工夫が必要でしょう。
判断のポイント: 一般的には、まず外来治療から開始し、経過や状態によって入院や他の施設利用を検討するのが現実的です 。外来で治療する中で「やはり自宅では難しい」となれば、担当医が入院可能な病院を紹介してくれるでしょう。また単身生活で支援者がいない場合や、家族が対応しきれない場合には、医療機関併設の回復施設(グループホーム)への入居を勧められることもあります 。これは自宅と入院の中間のような存在で、日中は仕事や通院をしつつ、夜間はルールのある共同生活を送ることで自律を促す場です。大石クリニックなど一部の専門機関では、こうしたグループホームと連携して治療パッケージを提供しています 。
複数の療法を組み合わせる意義
ギャンブル依存症の克服には一つの療法だけでは不十分な場合が多く、複数のアプローチを組み合わせることが効果的です 。例えば、個人カウンセリング(CBT)とグループ療法を並行して受けることで、お互いのメリットを享受できます。CBTで自分の問題点を深く掘り下げつつ、グループで仲間の話から学ぶという相乗効果が期待できます 。実際、個人治療のみより自助グループ参加やワークブック学習を併用した方が治療効果が高いことが報告されています 。
また、動機づけ面接で治療意欲を高めてからCBTに移行するといった段階的アプローチも有効です。一度に全部を始める必要はなく、最初はMIでエンジンをかけ、本人のやる気が出てきた段階でCBTや家族療法に取り組むとスムーズです。さらに、治療初期にはグループより個人面接の方が話しやすい人も、途中から仲間の重要性に気づきグループ療法に参加するようになるケースもあります。治療は動的なプロセスなので、固定的に考えず柔軟にメニューを組み替えていくことが大切です。
家族や自助グループとの併用: 依存症治療では本人の治療+家族への支援+自助グループ参加という三本柱が理想的とも言われます 。例えば、治療中に家族も別の専門家から助言を受けておけば、家庭でのサポート体制が整い治療効果が高まります。同時に、自助グループ(後述のGAなど)に通い始めると、治療終了後も継続的な支えが得られます 。専門家の治療はいつか終わりますが、自助グループは一生利用できます。治療で身につけたことを維持する場として、ぜひ活用を検討してください。
併用時の留意点: 複数のアプローチを並行する場合、情報共有と目標の統一が重要です。主治医やカウンセラーが複数いる場合は、お互いに治療方針が食い違わないよう連携します。また本人も「今自分は何に取り組んでいるのか」を整理しておきましょう。欲張りすぎて混乱すると元も子もありません。担当者とよく相談し、「この時期はこれに集中しよう」「次の段階ではこちらも試そう」とロードマップを描くと安心です。
家族・周囲の役割とサポート体制
家族やパートナーの関わり方も治療法選択の大きなポイントです。周囲の人ができるサポートとしては、大きく「問題を指摘し治療につなげること」「治療中に適切に支えること」の二段階があります。
治療への動機づけ: 多くの場合、家族が先に問題に気づき、治療を促す役割を担います 。賭けによる借金が膨らんだり嘘を重ねる様子を目の当たりにし、「このままではいけない」と感じるのです。しかし最初は「本人の意志が弱いだけ」と誤解してしまうことも多いため、まず家族が依存症は病気で専門治療が必要と理解することが大切です 。その上で、感情的に責め立てるのではなく冷静に、「専門家に相談しよう」と提案してみましょう。本人が拒否しても、家族だけで相談機関に行くこともできます。そこで対処法を教えてもらいながら、粘り強く受診を勧めることが重要です。
治療中のサポート: 本人が治療を開始したら、家族も協力体制を築きます。具体的には、浪費や再発を防ぐために経済的な管理を引き受けたり、通院の送り迎えやスケジュール管理を手伝う、日常生活のリズムを整える支援をする、といったことです。また心理的サポートとしては、本人の努力を認め小さな進歩でも褒めること、過去のことを蒸し返して責めすぎないことが大切です。家族もストレスを抱えているため、必要なら前述の家族療法や家族教室に参加し、プロの助言を得ながら自身のケアも行ってください。
境界線の設定: 支援と甘やかしは紙一重です。家族は毅然とした態度も求められます。例えば、また借金をしてきても肩代わりしない、嘘をついたら悲しい気持ちを伝える、といった適切な境界線を保つことです 。これは家族だけで判断が難しい場合も多いので、カウンセラーや自助グループで他の家族の体験を参考にしながら方針を決めると良いでしょう。
自助グループの活用と継続支援
自助グループとは、同じ悩みを持つ当事者同士が自主的に集まり、体験を語り合いながら回復を助け合う集まりです。ギャンブル依存症の代表的な自助グループにギャンブラーズ・アノニマス(GA)があります 。GAはアルコホーリクス・アノニマス(断酒会)をモデルに1957年に発足した世界的な組織で、日本国内にも現在200以上のグループが各地で定期的にミーティングを行っています 。
治療を検討する際、このGAなど自助グループへの参加も選択肢に必ず入れてください。理由は、自助グループは無料で長期にわたり利用できる貴重なリソースだからです。専門家の治療は期間が区切られますが、GAには何年でも通うことができます。ミーティングに長く参加し続けることで症状が安定し回復につながることが経験的にも知られています 。実際、国内外の多くの専門家が「ギャンブル依存症からの回復にはGA参加が最も大切」と口を揃えます 。
自助グループは治療ではありませんが、治療と平行して利用するのがおすすめです。週1回でもGAの仲間と会う機会を持てば、「また一週間賭けずに過ごせた」と実感できますし、仲間から励ましやアドバイスをもらえます。特に治療プログラムを終えて維持期に入った後は、GAが心の拠り所となって再発を防ぐ役割を果たします。もちろんGAだけでギャンブルをやめられる人もいますが(実際、自力で回復した人の少なくとも20%は専門家の治療を受けず自助グループ等で改善したという研究もあります )、治療+GAという二本柱で進めるとより確実でしょう。
家族向けには、ギャマノン(Gam-Anon)と呼ばれる自助グループがあります。こちらはギャンブル問題を持つ人の家族や友人が集い、情報共有や感情の吐露を行います 。家族同士で支え合うことで、「自分たちだけじゃない」と安心でき、適切な関わり方を学ぶことができます 。各地の精神保健福祉センターや依存症支援団体が家族会を紹介してくれるので、ぜひ利用を検討してください。
継続支援: ギャンブル依存症の克服はゴールが明確に訪れるものではなく、生涯にわたっての自己管理が求められる場合もあります。治療法の選択というテーマからは外れますが、「回復とはやめ続けている状態である」という認識を持ちましょう。一度問題行動が止まっても、気を抜けば再燃する可能性があります。ですから、治療で学んだことを習慣化し、支援者とのつながりを維持することこそが回復の秘訣です 。自助グループはまさにその場であり、また定期的にカウンセリングをフォローアップで利用するのも良いでしょう。
最後に、どの治療法を選ぶにせよ「今日からできる小さな一歩」を踏み出すことが大切です。悩んで立ち止まっているより、まずは身近な相談窓口に連絡してみてください。プロに繋がれば道筋が示されます。一人ひとりに合った回復プランは必ずあります。焦らず着実に、一歩ずつ取り組んでいきましょう。
オンラインカウンセリングや地方在住者向けサービスの活用
近年はインターネットの普及に伴い、オンラインで受けられるカウンセリングサービスも充実してきました。遠隔地に住んでいて近くに専門医療機関がない場合や、仕事・育児で通院時間が取れない場合でも、オンラインカウンセリングを活用すれば専門家の支援を受けることが可能です。実際、バーチャル相談(オンライン療法)は治療へのアクセス性を飛躍的に高めるとして注目されています 。
オンラインカウンセリングには、ビデオ通話や電話、メール相談など様々な形態があります。ビデオ通話であれば顔を合わせて話せるので対面に近い感覚で利用できます。対面よりリラックスできる、自宅から移動せず相談できる、といったメリットがあります。一方でプライバシーの確保(家族に聞かれない環境を用意する等)や通信環境の整備といった課題もありますが、最近ではアプリを使った手軽なカウンセリングも登場しています。
地方在住者向けの公共サービス: 日本では各都道府県の精神保健福祉センターや依存症相談拠点が、電話相談やオンライン相談に対応しています。例えば、厚生労働省が委託するギャンブル等依存症専門相談ダイヤルでは、年中無休24時間でフリーダイヤルの電話相談「0120-683-705」を受け付けています 。ここには臨床心理士などの有資格カウンセラーが待機しており、無料で悩みを聞いて必要な情報提供やアドバイスを行っています 。地方からでも気軽にかけることができますし、匿名で相談可能です。まずは電話で話をすることで心が軽くなり、その後の具体的な行動計画(受診先の紹介等)も得られるでしょう。
また、オンライン自助グループの活用も見逃せません。コロナ禍以降、GAのミーティングもZoomなどでオンライン開催される例が増えました。地域にミーティングが無い場合でも、オンラインで全国各地の仲間と繋がれます。掲示板やSNS上でのコミュニティも存在しますが、プライバシーや情報の正確性に注意が必要ですので、公認のオンラインミーティングを利用するのが安心です。
民間のオンラインサービス: 最近では民間企業やNPOによるオンライン相談サイトも増えています。例えば、オンライン専門のカウンセリングマッチングサービスでは、依存症に強いカウンセラーを検索し予約してビデオ通話で相談できるようになっています。料金は1時間あたり5,000〜10,000円程度が相場ですが、初回は低価格や無料相談を提供しているところもあります。英語圏ではBetterHelp等が有名ですが、日本でも「cotree(コトリー)」などが台頭してきており、自宅にいながらスマホひとつでプロと話せる環境が整いつつあります。
オンラインサービス利用時のポイント: 顔が見えない分、対面以上に信頼できる相手かどうかを見極めることが大切です。資格の有無や実績を確認し、初回に違和感があれば無理に続ける必要はありません。また、オンライン相談はあくまで通院治療の補完と考え、必要に応じて実際の医療機関受診も検討しましょう。特に薬の処方や診断が必要な場合、オンライン診療を実施している精神科もあります(初診からのオンライン診療は制限がありますが、フォローアップは可能な場合あり)。
地方在住者へのメッセージ: 「近くに専門医がいないから…」とあきらめないでください。上述のような電話相談、オンライン面接、さらには地域の保健師によるアウトリーチなど、地方でも受けられる支援は存在します。自治体によっては巡回相談を行っているところもありますし、交通費助成をして遠方の専門病院に繋いでくれる場合もあります。インターネット環境さえあれば都市部の専門家と話すこともできますので、ぜひテクノロジーや公的サービスを活用してみてください 。
おすすめの書籍・サービス紹介
最後に、ギャンブル依存症からの回復に役立つ書籍やサービスをいくつかご紹介します。知識を深めたい当事者や家族向けの本、そして相談先や自助グループなどのリソースです。必要に応じて活用し、理解を深めたり具体的な支援を得る足掛かりにしてください。
関連書籍
- 『ギャンブル依存症』(田辺 等 著, NHK出版) – 日本におけるギャンブル依存症研究の第一人者である田辺先生による解説書です。パチンコや競馬など具体例を交えながら、依存症の実態と治療・支援について分かりやすく述べられています 。ギャンブル依存症に関する新書として定番の一冊で、当事者にも家族にもおすすめです。
リンク
- 『ギャンブル依存症から抜け出す本 <イラスト版>』(樋口 進 著, 講談社) – 久里浜医療センターの樋口進医師(日本の依存症治療の権威)が監修した本です。イラスト図解で平易に書かれており、治療の流れや生活上の注意点、家族ができることまで網羅されています 。医療機関の探し方や相談窓口の一覧も掲載されており、具体的な実践に役立つ内容です。
リンク
- 『家族のための「ギャンブル問題」完全対応マニュアル』(田中 紀子 著, アルコール医療研究所) – ギャンブル依存症者を夫に持つ著者が、自身の経験と支援活動をもとに執筆した家族向けガイドです 。ギャンブル依存症とは何かから始まり、家族が取るべき対応(経済的措置、心構え、自助グループ参加の方法など)が具体的に示されています。絶望から希望へと変わった体験談は、多くの家族に勇気を与えるでしょう。
リンク
- 『ウルトラ図解 ギャンブル依存症』(法研) – 図表やイラストを豊富に使った入門書です 。専門用語が苦手な方向けに、病態から治療法、回復施設の紹介までビジュアルで理解できます。手軽に読めてポイントを掴めるので、家族や支援者が基礎知識を得るのにも適しています。
支援サービス・相談先
- ギャンブラーズ・アノニマス(GA)日本中央事務局 – ギャンブル依存症当事者の自助グループ。全国のミーティング情報やGAの基本的な考え方が公式サイトで案内されています。参加費は無料(献金制)で、予約も不要です。「とにかく話を聞いてほしい」「仲間が欲しい」という方は最寄りのミーティングに足を運んでみましょう。※家族向けのギャマノン情報も入手できます。
- 地域の依存症専門相談窓口 – 各都道府県の精神保健福祉センターや保健所などで、ギャンブル等依存症の相談を受け付けています。厚労省の委託事業「ギャンブル等依存症予防回復支援センター」では、Webサイト上で全国の相談窓口リストを公開しています 。お住まいの地域名と「ギャンブル依存 相談」と検索すると窓口情報が出てきますので、まずは電話やメールで問い合わせてみてください。
- ギャンブル依存症相談専用ダイヤル(24時間全国対応) – 上述の通り、0120-683-705 に電話すれば、365日いつでも無料で専門家に相談できます 。匿名OKで、家族からの相談も可能です。「病院に行くほどではないかも…」と迷っている段階でも構いません。困ったときはまずここに電話すれば、適切なアドバイスと必要な情報提供が受けられます。
- 依存症専門医療機関・回復施設 – ギャンブル依存症の治療実績がある専門病院やクリニック、リハビリ施設が全国に点在しています。代表的な施設として、国立病院機構久里浜医療センター(神奈川)、成増厚生病院(東京)、大石クリニック(大阪)、北仁会依存症治療病棟(北海道)などが挙げられます。これらの医療機関では外来から入院、家族支援、社会復帰支援まで総合的なプログラムを提供しています。住んでいる地域に専門機関が無い場合でも、紹介状を持って遠方の病院を受診するケースもあります。依存症対策全国センター(久里浜)や各地の精神保健福祉センターに問い合わせれば、適切な医療機関の情報が得られます 。
- オンラインカウンセリングサービス – 民間のオンライン相談プラットフォームを利用すれば、自宅から専門カウンセラーと面談できます。例えば「cotree(コトリー)」では公認心理師や精神科医とマッチングし、ビデオ通話やテキストで相談可能です。他にも「ボイスマルシェ」「BetterHelp(英語)」など選択肢があります。必ずしも依存症専門とは限りませんが、「行動嗜癖の相談経験あり」等のプロフィールを参考に選ぶと良いでしょう。地方でも質の高い心理支援を受けられる手段として今後さらに普及が期待されます 。
ギャンブル依存症の克服は決して簡単ではありません。しかし、適切なカウンセリングやセラピーを受け、周囲のサポートを得ながら取り組めば、必ず回復への道が開けます。実際に多くの人が専門家の助けや仲間の支えによって賭けない生活を取り戻しています。大切なのは「一人で抱え込まないこと」「できる支援は何でも活用すること」です。この記事で紹介した療法やサービスが、あなた自身や大切なご家族の回復プランを考える一助になれば幸いです。勇気を持って第一歩を踏み出し、専門家と繋がってください。 必要なときにはいつでも支援の手があります。あなたは決して一人ではありません。