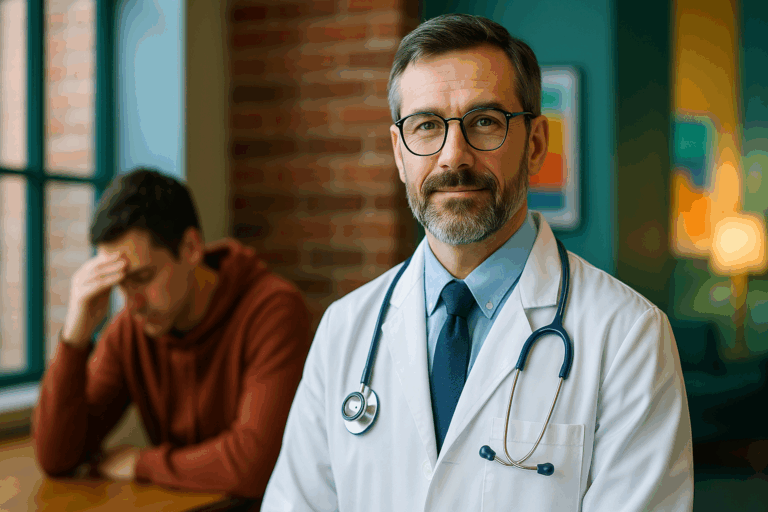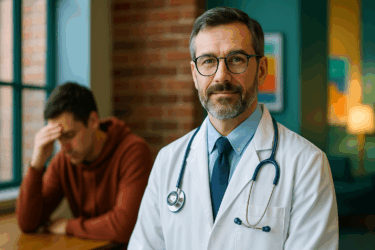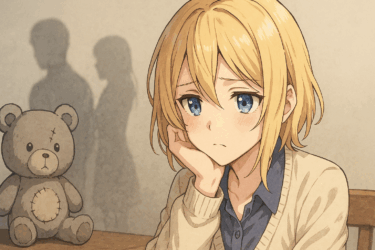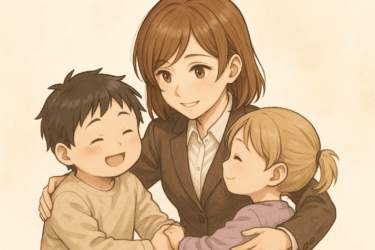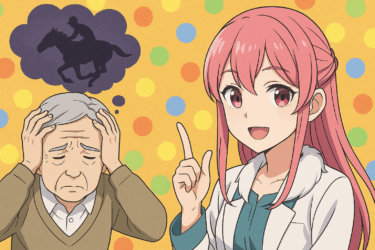はじめに
ギャンブル依存症(ギャンブル障害)は適切な治療と支援によって回復が十分に可能な疾患です¹。しかし現状では、日本の成人の約0.8%(推計約70万人)が過去1年以内にギャンブル依存症が疑われる状態を経験したと報告されており²、多くの当事者と家族が支援を必要としています。近年、ギャンブル依存症はアルコールや薬物の依存症と同様に医学的な「嗜癖(しへき)」として位置づけられ、専門治療の重要性が認識されています。 以下では、最新の治療法と日本における治療体制、リカバリー施設について専門的な知見に基づき解説します。
ギャンブル依存症の治療法:最新動向とエビデンス
心理療法(精神療法)を中心としたアプローチ: 現在、ギャンブル依存症に対しては心理社会的治療が治療の柱です。アルコールや薬物依存症では渇望を抑える薬剤が開発・使用されていますが、ギャンブル依存症に有効な薬物療法は確立されていません³ 。そのため、専門医は「薬では解決できない問題は精神療法の中で向き合う必要がある」と強調しています³ 。具体的に有効性が示されているのは、認知行動療法(CBT)や動機づけ面接法(MI)などの心理療法です。認知行動療法では賭博への欲求に対処するスキルや、ギャンブルに対する認知の歪みを修正し、再発予防の行動様式を身につけます³ 。動機づけ面接法は治療への意欲が低い患者に対して内在的動機づけを高める技法で、短期介入でも長期にわたりギャンブル行動の改善効果が持続することが報告されています 。加えて、日本独自のアプローチとして内観療法(自己の内省を深める療法)が活用されることもあります³ 。
集団療法と自助グループの活用
ギャンブル依存症治療では集団療法(グループミーティング)の効果が高く評価されています³ 。同じ問題を持つ患者同士が体験を共有し、互いに支え合うことで内省を深め、行動変容を促す効果があります。専門クリニックなどでは集団認知行動療法のプログラムが導入されつつあり、標準的治療プログラム「STEP-G」(Standardized Treatment Program for Gambling Disorder)と呼ばれるグループ療法マニュアルも開発されています 。実際、民間支援団体代表の田中紀子氏は「回復に最も効果的なのは同じ経験を持つ人同士のグループセラピーだ」と述べており、薬物療法がない現状ではミーティングを重ねることが唯一の治療法だと強調しています² 。ギャンブラーズ・アノニマス(GA)などの自助グループも全国に約200団体存在し² 、定期的なミーティングに根気強く参加し続けることで「賭けない生活」を維持できると報告されています² 。専門医も「同じ問題を持つ仲間との定期的なグループミーティングを長期に持続することが最も大切」と述べており³、自助グループへの参加は治療の重要な一環と位置づけられています。
家族療法・家族支援の重要性
ギャンブル依存症は本人だけでなく家族にも深刻な影響を及ぼすため、家族療法や家族支援プログラムも欠かせません。家族が適切に対応し支えることで、治療効果が高まることが知られています。アメリカで開発されたCRAFT(コミュニティ強化アプローチと家族トレーニング)は、依存症者の家族のためのプログラムで、日本でも近年導入が進んでいます。CRAFTでは家族が自身のコミュニケーション法を工夫し、対立を避けつつ本人を治療につなげるスキルを学びます 。実際、依存症医療の第一人者である樋口進医師は「ギャンブル依存症から抜け出すには家族が主体的に動くことが大切」であり、医療機関でカウンセリングや認知行動療法を受ければ「本人の行動パターンや考え方は少しずつ変わっていく」と述べています⁴ 。家族が適切な支援を行うことで、借金問題への対処や再発防止にも大きな効果があります。家族向けの自助グループ(ギャマノン)も各地に組織されており、同じ悩みを持つ家族同士が情報交換や支え合いを行っています。
薬物療法の現状
前述の通り、ギャンブル依存症に対する国内で承認された薬物療法は存在していません³ 。しかし最新の研究動向として、海外ではいくつかの薬剤がギャンブル行動の抑制に効果を示す可能性が報告されています。例えば、モルヒネ拮抗薬であるナルトレキソンやナルメフェンは賭博衝動を抑える作用により有望視されており、プラセボ対照試験で症状の改善効果が示されたとの報告があります⁶ 。また、抗うつ薬(SSRI)や気分安定薬、抗精神病薬(オランザピンなど)も少数の臨床試験で検討されています⁶ 。ただし、こうした薬物療法のエビデンスは現時点で限定的かつ質が十分とは言えず⁶ 、標準治療として確立するには至っていません。専門医療の現場でも薬物療法は補助的な位置づけにとどまり、やはり中心となるのは認知行動療法に代表される精神療法と社会的支援であるという点は変わりません。
日本における治療体制:依存症治療拠点と専門外来
専門治療機関と依存症外来
日本では近年、ギャンブル依存症に対応できる専門医療機関の整備が進みつつあります。国の指定する「依存症専門医療機関」では、アルコール・薬物・ギャンブル等依存症の専門治療プログラムを提供しています。例えば、国立病院機構久里浜医療センターは我が国最大規模の依存症専門治療拠点であり、2013年に国内初のギャンブル依存症治療専門部門を開設して以来、外来・入院プログラムによる治療と臨床研究の両面で中心的役割を果たしています 。久里浜医療センターでは週1回×全6回の認知行動療法プログラムを軸に、必要に応じて9週間程度の入院治療も実施しています。 プログラムには、生活指導や作業療法、SST(社会生活技能訓練)、アンガーマネジメント教育、さらに症状に応じてアルコールやニコチンの併存問題への対応、外出訓練やGA(自助会)への参加支援などが組み込まれており 、医学的治療と社会復帰支援が一体となった包括的ケアを提供しています。
また、各都道府県に設置された精神保健福祉センター(全国で69か所)でも、ギャンブル依存症を含む嗜癖問題に関する相談・治療支援が行われています³ 。近年、厚生労働省は都道府県ごとに「依存症治療拠点機関」を指定し、地域の医療機関や保健所、自助グループ等との連携拠点とする取り組みを進めています 。例えば東京都では、昭和大学附属烏山病院がギャンブル等依存症の専門医療機関および治療拠点機関に選定され、専門外来による治療や研修・情報発信の中核を担っています 。このような専門外来(依存症外来)は、他の精神科診療科目の中に設けられる形で大学病院や精神科病院、クリニックにも徐々に広がっています。
治療資源の不足と今後の課題
もっとも、ギャンブル依存症の患者数に対して治療可能な医療機関はまだまだ不足しているのが現状です³ 。専門外来や入院病棟を持つ医療機関の数は限られており、地域によっては適切な治療にアクセスしづらい状況があります。そのため、自助グループや民間の回復支援施設など医療以外の支援資源を有効に活用し、医療機関と連携して継続的なフォローアップを行っていくことが重要です。2018年には「ギャンブル等依存症対策基本法」が施行され、国を挙げての依存症対策推進が図られています。直近の基本計画(令和7年3月策定)でも、相談窓口の整備や民間団体への支援強化、依存症専門医療機関の拡充などが盛り込まれており 、今後さらに治療環境の充実が期待されます。
リカバリー施設の種類と機能
リカバリー施設とは: 医療機関での治療と並行して、回復期の当事者を支えるリカバリー施設の役割も重要です。リカバリー施設とは、依存症からの回復を目指す人が一定期間集団生活を送りながらプログラムに取り組む場であり、賭けない健全な心と規則正しい生活習慣を取り戻すことを目的とした施設です⁵ 。入所期間は個人差がありますが、約1年半から3年程度かけてじっくりとリハビリを行うケースが多いとされています⁵ 。日中はグループミーティングや12ステッププログラム(GAのプログラムに準じたもの)が活動の中心となり、夜間も自助グループ参加やミーティングを継続します⁵ 。また、スポーツや地域ボランティアへの参加を通じて他者との関わり方や社会性を身につけ、社会復帰に向けた生活訓練や就労支援も受けられます⁵ 。このようにして「賭けない生き方」の実践を重ね、退所後の自立を目指すのがリカバリー施設の基本機能です。施設によっては、回復者がそのままスタッフとして働き後輩を支援する道も用意されています⁵ 。
入所型と通所型
リカバリー施設には、大きく入所型(居住型)と通所型の2種類があります。入所型は本人が施設に寝泊まりしながら集中的にプログラムに取り組むもので、生活環境を変えてギャンブルから距離を置きたい場合や、家庭環境の問題で自宅での断賭が難しい場合に適しています。 一方、通所型は自宅や自立生活を維持しながら日中のプログラムに通う形式で、仕事を続けながら治療したい場合や、ある程度日常生活の基盤があるケースに用いられます。 通所型施設では週数回のカウンセリングやグループワークに参加し、夕方以降は自助グループ(GA)のミーティングに出席するといったスケジュールが一般的です。症状や生活状況によって入所と通所を組み合わせる柔軟な利用も行われており、たとえば平日は働きながら夜だけ施設でプログラムを受けて泊まり込むという形でリハビリを続けることも可能です 。
民間施設と公的施設
リカバリー施設の運営主体には、NPO法人などの民間団体と自治体等の公的機関があります。民間の回復施設としては、薬物依存症の領域で広く展開してきたDARC(Drug Addiction Rehabilitation Center)やマック(MAC)といった自助的施設が、アルコール・薬物と併せてギャンブル依存症者を受け入れている例が多く見られます 。例えばNPO法人マックが運営するデイケアセンターや、救世軍(サルベーション・アーミー)の自省館などは、ギャンブル問題を含む依存症全般の回復支援プログラムを提供しています 。一方、近年ギャンブル依存症に特化した民間施設も登場しており、山梨県の「グレイス・ロード」⁵ や長崎県の「グラフながさき」⁵ などがその例です。グレイス・ロードでは日中のデイケアと夜間のナイトケアを組み合わせ、GAミーティングへの参加を必須とした独自のプログラムを実践しています⁵ 。これら民間施設の多くは利用料がかかりますが、生活保護受給者や経済的困窮者を受け入れている所もあり、運営資金は寄付や行政からの委託事業で賄われることもあります。
公的なリカバリー支援としては、自治体や社会福祉法人が運営する自立訓練施設・回復支援施設が挙げられます。例えば地方自治体によっては、医療機関退院後の依存症者を対象に一定期間住まいとリハビリプログラムを提供する更生施設を設置している場合があります。また、精神保健福祉センターや保健所が主体となってデイケアプログラム(通所リハビリ)を提供し、医療と地域生活支援の橋渡しをするケースもあります。公的施設は費用負担が軽減され利用しやすい反面、定員や所在地が限られるため希望者全員が利用できる状況にはないのが実情です。こうした背景から、国は民間の回復支援団体に対する補助金交付など支援策を強化しています 。民間と公的機関が有機的に連携し、「治療から社会復帰まで」途切れのない支援体制を構築することが今後の課題です。
おわりに:専門的支援と継続的なフォローの重要性
ギャンブル依存症は本人の意思だけで治すことが難しい疾患ですが、専門治療と周囲のサポートによって回復への道筋を歩むことができます¹ 。精神療法や家族支援、社会復帰プログラムを組み合わせた総合的アプローチにより、多くの方が「賭けない生活」を取り戻しつつあります。治療の現場では、「本人が変わる」だけでなく「家族や支援者も学びながら伴走する」ことが重視されています⁴ 。また、回復は短期で完結するものではなく、少なくとも数年単位の長期的なフォローアップが必要です² 。専門医やカウンセラー、自助グループ、リカバリー施設など、さまざまな資源を積極的に活用しながら、社会全体でギャンブル依存症からの回復を支えていくことが大切です。医療・福祉関係者にとっても、最新の知見に基づいた治療法の習得と地域資源との連携が求められています。本記事の情報が、ギャンブル依存症に悩む当事者やご家族、支援者の方々にとって回復への一助となれば幸いです。
参考文献(References)
- 消費者庁「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」(中央労働委員会)
- 田中紀子「ギャンブル依存症対策を強化へ~民間支援団体代表に聞く」(時事メディカル)
- 田辺等先生に「ギャンブル依存症」を訊く(日本糖尿病学会)
- Dowling, N.A. et al. “Pharmacological interventions for the treatment of disordered and problem gambling.”(medRxiv)
- ギャンブル依存症ポータルサイト(kakenai.jp)
- Dowling, N.A. et al. “Pharmacological treatments for disordered and problem gambling.” Cochrane Database of Systematic Reviews (2019; Issue 4: CD008936)