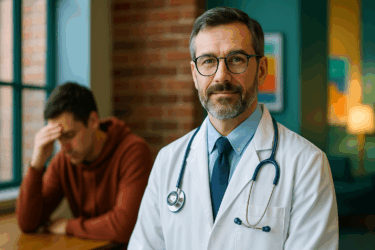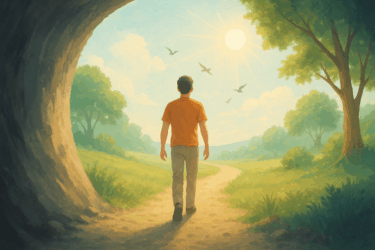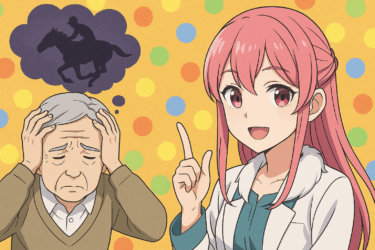ギャンブル依存症とは、自分の意思ではギャンブルをやめられなくなり、生活に重大な悪影響が出ても賭け事を続けたい衝動を抑えられない精神疾患です。パチンコや競馬などにのめり込みすぎて借金を重ね、人間関係や仕事にも支障を来たす状態で、自分ではコントロールできなくなったものを指します。アルコール依存症やうつ病と同じく国際的に正式な“病気”として認められており、米国精神医学会(APA)は診断基準を定め、WHOも「治療すべき病気」と位置付けています。日本では生涯で約3.6%(約320万人)の人がギャンブル依存症に陥ったことがあるとの調査もあり、決して珍しい病気ではありません。以下では、その症状や自己チェック方法、対処法について詳しく解説します。
ギャンブル依存症の診断基準(DSM-5)
医学的には「ギャンブル障害」として定義されており、診断にはDSM-5(精神疾患の診断統計マニュアル第5版)の基準が用いられます。DSM-5では過去12か月間に以下のような行動や症状が9項目中4つ以上当てはまる場合にギャンブル障害と診断されます。主な診断項目は次のとおりです:
- 賭け金や賭ける時間が次第にエスカレートする。より強い興奮を求めて、少額では物足りずに賭ける額を増やしがちになる。
- ギャンブルをやめたり減らしたりしようとすると落ち着かない。途中で中止するとイライラしたり不安になったりする。
- ギャンブルを節制・中止しようとしてもできない。何度も減らそう・止めようと試みても失敗してしまう。
- 常にギャンブルのことで頭がいっぱいになる。過去の勝敗を繰り返し考えたり、次に賭ける計画を練ったり、ギャンブル資金の工面を常に考えたりする。
- 嫌な気分を紛らわすために賭けてしまう。ストレスや不安、落ち込みなど気分が悪いときにギャンブルに走りやすい。
- 負けを取り返そうとする(いわゆる「追い掛け」行為)。ギャンブルで負けた直後に、失った分を取り戻そうと別の日にまた賭けを行う。
- ギャンブルにのめり込んでいることを隠すために嘘をつく。家族や友人に対し、ギャンブルの頻度や負け額をごまかすための嘘を重ねる。
- ギャンブルが原因で大事なものを失いかけている。賭博のために人間関係が壊れたり、仕事や学業の機会を台無しにしたことがある。
- ギャンブルによる経済的危機を他人に救ってもらおうとする。借金の穴埋めを周囲に頼ったり、生活費の工面が自力でできなくなっている。
以上がDSM-5における主な診断基準です。このような状態に複数該当すれば、専門家の診断では「ギャンブル障害(ギャンブル依存症)」と判断されます。次の章では、こうした症状がどのように現れ、進行していくかを初期から重度まで段階的に見ていきましょう。
初期症状 – ギャンブル依存症の兆候
ギャンブル依存症は進行性で自然に治ることはない病気だとされています。発症の初期段階では、当初は娯楽として楽しんでいたギャンブルの動機が変質してくることが引き金になります。具体的には、次のような兆候が現れ始めます。
- 賭け事への熱中度が増し、のめり込みが強くなる。「もう一回だけ」「次は勝てる」と考え、当初予定していた時間や金額を超えてギャンブルを続けてしまいます。
- より大きな刺激を求めるようになる。最初は少額の賭けでも興奮できていたのに慣れてしまい、もっと大金を賭けないと満足できなくなることがあります。
- 嫌な気分を晴らす手段としてギャンブルを使う。不安やストレスがあるときに「賭ければ落ち着く」と感じ、ギャンブルを精神安定剤代わりにし始めます。この段階になると「楽しくなくなったからやめる」というブレーキが効きにくくなり、ギャンブルが習慣化してしまいます。
- ギャンブルのことが頭から離れなくなる。日常生活の中でも勝敗のことばかり考えたり、次は何に賭けようかと常に考えている自分に気付くことがあります。趣味や仕事中でも集中できず、心がギャンブルに支配され始めている状態です。
こうした初期症状では、本人はまだ自覚が薄かったり、「自分はまだ大丈夫」「いつでもやめられる」と問題を否認しがちです。しかし動機の変化や生活への影響が出始めた段階で、既に依存症への坂道を下り始めている可能性があります。次に、中期~進行期のサインを見てみましょう。
進行期のサイン – 深刻化する行動
依存症が進行していくと、ギャンブル行動は次第にエスカレートし、周囲から見ても異常な状態になっていきます。主な進行期のサインには以下のようなものがあります。
- 負けても止められず、「取り返そう」と繰り返す。一度大敗しても、その損を埋めようと翌日以降にまた賭けてしまう「負け惜しみの追い掛け」行動が増えます。この「負けを取り戻したい」という強迫的な思考は、もはや依存症の典型症状といえます。
- 隠し事と嘘が増える。ギャンブルへの支出や遊んでいた時間をごまかすために、家族に嘘をつく場面が増加します。負けたのに「今日は勝った」などと虚偽を報告したり、レシートや馬券を隠すなど、秘密主義が強まるのも特徴です。
- 借金や金銭トラブルが発生し始める。手持ちのお金が尽きてもギャンブルを続けるため、サラ金から借りたりクレジットカードで現金化するなどして資金繰りに走ります。生活費や貯金にも手を付けるため、家計が乱れ始め、家族とお金のことで口論になるケースも増えます。
- 生活習慣や責任の放棄。ギャンブル最優先の生活となり、仕事や学校を無断で休む、家族との時間を犠牲にする、趣味や約束事を後回しにするといった行動が見られます。これにより成績不振や職場での評価低下にもつながり、さらにストレスが溜まる悪循環に陥ります。
進行期になると、周囲の人も異変に気付き始めます。家族や友人から「最近様子がおかしい」「ギャンブルのしすぎでは?」と指摘や非難を受けることも増えるでしょう。本人も内心では罪悪感や危機感を抱き始めますが、自力ではますます制御不能の状態に陥っていきます。この段階で適切な対処をしないと、さらに深刻な破綻を招きかねません。
重度のサイン – 生活への深刻な影響
ギャンブル依存症が重症化すると、経済的・社会的・精神的に極めて深刻な状況に至ります。重度のケースで見られる主なサインは次のとおりです。
- 莫大な借金や経済的破綻。ギャンブルにより借金が雪だるま式に膨らみ、消費者金融への多重債務やクレジットカードの延滞が重なります。貯金は底を突き、家計は崩壊寸前となります。状況によっては、借金返済のために盗みや詐欺に手を出してしまうこともあり、取り返しのつかない事態を招きかねません。
- 人間関係の崩壊。配偶者や家族の信頼は完全に失墜し、離婚や家庭崩壊に至るケースも少なくありません。友人も愛想を尽かし、孤立状態に陥ります。仕事でも重大なミスや横領など問題行動を起こし失職することがあり、社会的な居場所を失ってしまいます。
- 心身の不調と絶望感。経済的・社会的行き詰まりから、うつ病や不安障害を併発する人が非常に多く、約半数はうつ状態になるとも報告されています。将来への絶望から自殺を考える人も珍しくなく、ある研究では生涯に自殺未遂を図る人が40%に及ぶとのデータもあります。このように精神的にも追い詰められ、健康も害してしまうのです。
重度になると、もはや本人の意思だけで抜け出すのは極めて困難です。生活が破綻し、自暴自棄になる人もいます。しかし適切な治療と支援を受ければ回復は不可能ではありません。次章では、自分でできるチェックリストと、問題に気付いた後の対処法を説明します。
ギャンブル依存症自己診断チェックリスト
ご自身(または家族)がギャンブル依存症かもしれない…と不安に感じている方は、以下の自己診断チェックリストを試してみましょう。過去12か月間の状況について、当てはまる項目がいくつあるか数えてみてください。これは前述のDSM-5の診断基準や、専門機関で用いられるスクリーニング質問をもとに作成したチェックリストです。
⇒ 結果: いかがでしたか。上の項目で「当てはまる」ものが0~1個の場合、今のところ依存症の可能性は低いと考えられます。2~3個当てはまる場合は注意信号です。問題が始まりかけている恐れがあり、このままギャンブル行動が続けば依存が進行するリスクがあります。4個以上当てはまった方は、ギャンブル依存症の可能性が高いと言えるでしょう。特に6~7個以上該当する場合、既にかなり深刻な依存状態に陥っていると考えられます。自分はもちろん、身近なご家族が当てはまった場合も、一刻も早く対策を講じることが大切です。
セルフチェックの留意点
このチェックリストはあくまで簡易的な自己診断です。項目に当てはまる数が多いほど依存の可能性は高まりますが、正式な診断には専門家による評価が必要です。「まだ大丈夫」と自己判断せず、不安を感じた段階で専門機関に相談することが重要です。
チェック後の対処法 – 相談先と治療について
もし上記のチェックで依存の兆候が疑われたら、早めに行動を起こしましょう。ギャンブル依存症は本人の意思だけで治すことが難しい病気ですが、適切なサポートを受ければ回復できます。以下に、具体的な相談先や治療・支援の方法を紹介します。
- 専門の相談窓口に連絡する: まずはひとりで抱え込まず、専門機関に相談してみましょう。各都道府県の精神保健福祉センターや保健所には、依存症に関する相談窓口があります。プライバシーは守られますので、現状や不安を正直に話してみてください。加えて、国の依存症相談電話も利用できます。例えば、厚生労働省委託の「ギャンブル依存症予防回復支援センター」では、年中無休24時間対応の無料電話相談(サポートコール:0120-683-705)を行っています。臨床心理士など有資格のカウンセラーが匿名で悩みを聞き、必要な助言をしてくれます。誰にも言えずに苦しんでいる方は、まずは電話で声に出してみるだけでも大きな一歩となるでしょう。「どこに相談すればいいかわからない」という場合も、上記窓口に連絡すれば適切な支援先を案内してもらえます。
- 専門医療機関を受診する: 可能であれば、依存症治療の経験がある精神科・心療内科を受診しましょう。近年、各地域で依存症専門医療機関や専門外来が整備されつつあります。医師による診断のもと、精神療法(カウンセリング)や必要に応じた薬物療法が受けられます。ギャンブル依存症の治療では、賭博に至る考え方の癖を修正する認知行動療法や、衝動をコントロールする訓練などが有効とされています。また、うつ病など併存症がある場合にはその治療も並行して行います。専門医と相談しながら、適切な治療プランを立てていきましょう。
- 自助グループに参加する: ギャンブル依存症は仲間の支えが回復に大きな力を発揮します。同じ悩みを持つ人たちが集まり、お互いの経験と励ましを分かち合う自助グループ(ミーティング)に参加してみましょう。有名なものにギャンブラーズ・アノニマス (GA)という自助グループがあり、各地で定期的にミーティングが開かれています。最初は勇気がいるかもしれませんが、「自分だけじゃない」と実感できることで孤独感が和らぎ、先輩たちの体験談から問題克服のヒントが得られます。家族向けの自助グループ(ギャマノン等)もありますので、本人だけでなく周囲の方も利用できます。
- 生活環境の見直しと支援体制の構築: 賭け事に誘惑される環境から距離を置く工夫も必要です。例えば、金銭管理を家族に任せる、ギャンブル仲間との付き合いを控える、パチンコ店の前を通らない経路にする、といった対策があります。また、家族や支援者と誓約書やルールを決めるのも効果的です(例:「給与の管理は配偶者が行う」「ひとりで競馬場に行かない」等)。周囲の協力を得て、再発防止の仕組みを作りましょう。
- 家族・周囲の対応: ご家族が当事者の場合、家族だけで問題を抱え込まないことが大切です。専門機関への相談や自助グループ参加などを通じて、家族も正しい知識とサポートを受けましょう。経済的援助の際は要注意です。借金の肩代わりなどは一見本人の助けになるようですが、実は問題を長引かせる場合があります。むしろ借金と向き合い、弁護士や消費生活センター、司法支援センター(法テラス)などに債務整理の相談をするよう促すことが重要です。家族自身も疲弊しないよう適度に距離を保ちつつ、専門家の助言を得ながら本人の回復を支えていきましょう。
最後に、ギャンブル依存症は「意志が弱い人の道楽」ではなく、誰もが陥り得る病気です。恥ずかしいことでも珍しいことでもありません。適切な対処をすれば必ず改善への道は開けます。問題に気付いた今が回復への第一歩です。一人で悩まず、ぜひ今回紹介した相談先や支援を活用してみてください。早期の対応が、あなた自身と大切な家族の未来を守ることにつながります。勇気を出して一歩踏み出しましょう。
参考文献
- 「ギャンブル依存症」とは |ご存じ?Q&A – 大阪同和・人権問題企業連絡会
ギャンブル依存症の定義や特徴、国内調査結果について解説した記事。 - ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ – 消費者庁
ギャンブル依存症の概要やその影響について説明。 - 「ギャンブル依存症」について – ながはまメンタルクリニック
精神科医によるコラム記事。ギャンブル依存症の症状やDSM-5基準についてわかりやすく解説。 - ギャンブル障害 DSM-5を用いたチェックリスト – 依存症ピアネット・ソーバーねっと
DSM-5の診断基準9項目を日本語化した自己チェックリスト(オンライン質問票)。 - ギャンブル依存症 診断チェック(修正・日本語版SOGS) – 大石クリニック
世界的に用いられるSOGSというギャンブル依存症スクリーニングテストの日本語版。16項目の質問と採点・判定基準が掲載。 - ギャンブル依存症と重複しやすい精神疾患について – 国立病院機構 久里浜医療センター 依存症対策全国センター
久里浜医療センターによる専門資料。DSM-5の基準や国内有病率、併存症(うつ病・自殺企図率等)に関するデータを含む。 - サポートコール(24時間相談電話) – ギャンブル依存症予防回復支援センター
国が設置した依存症相談窓口。年中無休・24時間対応の無料電話相談について案内ページ。 - ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ – 消費者庁
ギャンブル依存症に関する公的支援情報。相談窓口や家族の対応、再発防止に向けたポイントなどを紹介するページ。