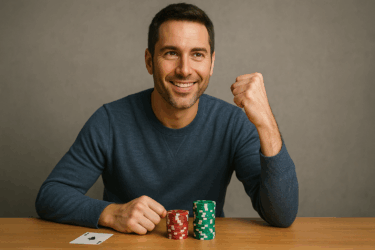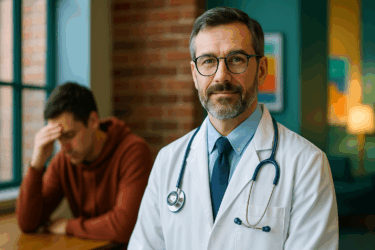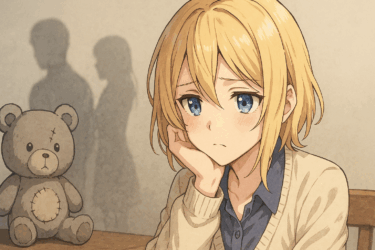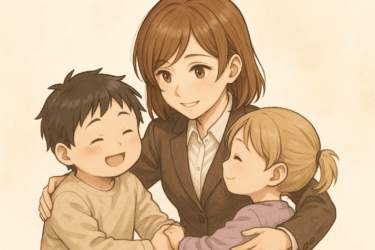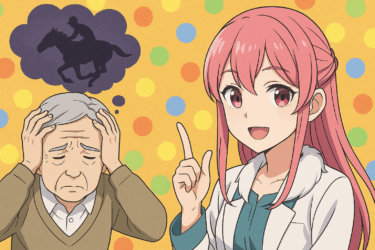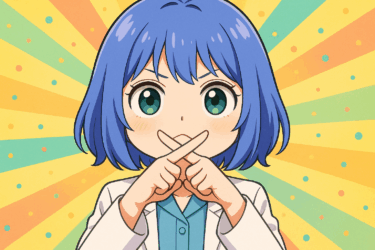ギャンブル依存症(正式には「ギャンブル障害」)は本人だけでなく家族にも深刻な影響を及ぼす病気です。日本では成人の約1.6~2.2%がギャンブル依存症と推計され、家族や恋人など周囲の人を含めると国民の約14%が何らかの形でギャンブル問題の影響下にあるとも言われています¹ 。決して珍しい問題ではなく、多くの家庭で信頼関係の崩壊や経済的・精神的な負担といった苦しみが生じています¹ 。もしあなたの大切な家族がギャンブル依存症かもしれないと悩んでいるなら、どうか一人で抱え込まないでください。同じ悩みを持つ人は他にもおり、適切な知識とサポートによって状況は改善し得ます。この記事では、家族が感じる心理的負担、その際に避けるべき対応と理由、そして家族としてできるサポート方法について解説します。さらに、専門のカウンセリングや自助グループ(家族会)の活用法や、よくある質問へのQ&Aも紹介します。あなたの苦しみに寄り添いながら、信頼できる情報をお届けします。
ギャンブル依存症で家族が負う心理的負担と特徴
ギャンブル依存症の問題に直面した家族は、計り知れない心理的負担を抱えがちです。その特徴として、以下のような状態に陥りやすいと言われています² :
- 常に不安で心が休まらない: 本人の一挙一動が気になって頭から離れず、「今もギャンブルをしているのでは?」「また借金をしているのでは?」と何もない時でも疑心暗鬼になってしまいます² 。常に最悪の事態を警戒し、心休まる時がありません。
- 自分のことが後回しになる: 家族が振り回されて、自分自身の考えや感情、生活を後回しにしてしまいます² 。趣味や友人との時間も減り、家族の人生そのものがギャンブル問題中心になりがちです。
- 過剰に干渉・監視してしまう: 不安や不信感のあまり、本人のお金を管理したり「今日もパチンコに行ったの?」と詰問したり、外出の後をつけるなど、行動を必要以上に監視してしまいます² 。なんとかギャンブルを止めさせようと必死になるあまり、家族自身が疲弊してしまいます。
- 慢性的なストレスと絶望感: 繰り返される嘘や借金発覚により、家族は常にストレスにさらされます。何度話し合っても裏切られる経験から、「このままでは家族が壊れてしまうのでは」と強い絶望感や孤独感を抱くこともあります。信頼していた家族による裏切りは精神的ショックが大きく、家族自身がうつ状態になるケースもあります¹ 。
こうした心理状態に家族が陥ってしまうことは決して珍しくありません²。家族の誰もが「なぜ自分たちだけがこんな目に…」と孤独に感じがちですが、実際には多くの家族が似たような苦しみを抱えています¹ 。問題が長期化すると、家族側も心身の健康を損ないかねません。まずは「家族もまた被害者であり、大きな負担を負っている」ことを自覚し、自分たちだけの責任ではないと理解することが大切です(※この点については後述します)。次章では、そうした極限状態の中で家族がつい取りがちな行動のうち、実は逆効果になってしまう対応について見ていきましょう。
家族がやってはいけない対応とその理由
絶望的な状況を前に、家族は何とか事態を好転させようと様々な行動に出がちです。しかし、中には本人のためにならないどころか問題を悪化させてしまう対応もあります。専門家は以下のような対応は避けるべきだと指摘しています。
- 借金の肩代わりをしない(イネーブリングの禁止): 家族としては「助けてあげたい」という一心で本人の借金を肩代わりしたり経済的に尻拭いしたりしてしまいがちです。しかし、たとえ愛情から出た行動でも、代わりに責任を取って借金を清算してしまうことはギャンブル依存を長引かせるだけです² 。これは「イネーブリング(enabling=問題行動を可能にしてしまう行為)」と呼ばれ、家族が手を出し過ぎることで本人が自分の問題に直面しなくなってしまいます² 。一時的に借金が消えて本人はホッとするかもしれませんが、「なんとかなる」という経験だけが残り、結局またギャンブルを再開してしまうのです² 。本人が本当に困って「自分で何とかしなければ」と痛感する機会を奪わないことが大切です。苦しくても借金の始末は本人に任せ、自己責任で向き合わせることで初めて回復への第一歩が生まれます⁵ 。家族が連帯保証人でない限り法的な返済義務もありませんので、専門家に相談しつつ毅然とした態度で臨みましょう⁵ 。
- 問題を隠したり世話を焼き過ぎない: 家族として恥ずかしい、周囲に知られたくないという思いから、つい問題を隠そうとしたり後始末に奔走したりしてしまうことがあります。しかし、ギャンブルによる欠勤を会社に嘘の連絡でごまかす、貸してくれた知人に家族が代わりに頭を下げて回る、といった対応は根本的解決にならないばかりか、かえって本人が問題の深刻さを実感できなくなります。過度な干渉や過保護も同様で、家族がなんでも管理・禁止しようとすると本人はかえって反発したり隠れて問題行動を続けるだけです。家族が「本人の人生の問題を代わりに背負い込まない」よう注意しましょう。本人のためを思ってやったことが結果的に本人の自立を妨げていないか、一度立ち止まって考えてみることが重要です。
- 感情的に責め立てない: 重大な裏切り行為を目の当たりにすれば、家族が怒りや失望で激しく非難してしまうのも無理はありません。しかし「いい加減にして!」「意志が弱いからだ」などと責め立てるだけでは、本人は罪悪感から更に隠れてギャンブルを続けたり「自分はダメな人間だ」と自己否定感を深めるだけの場合が多いです。依存症は意志の強さ弱さの問題ではなく、脳の働きが変化してコントロールが効かなくなる病的な状態です⁵ 。本人を頭ごなしに非難すると逆効果になりやすいため、後述するように冷静に働きかけることを心がけましょう。どうしても感情が抑えられない時は、いったんその場を離れて落ち着いてから話すようにすることも有効です。
- 家族だけで抱え込まない: ギャンブル依存症は家族にとっても「恥」のように感じられ、誰にも相談できず孤立しがちです。しかし、家族が社会から孤立してしまうと問題はますます深刻化します² 。経済的にも精神的にも限界を迎える前に、ぜひ周囲の信頼できる人や専門機関に相談してください。「全国ギャンブル依存症家族の会」のような家族同士の集まりでは「一人で悩まず、一緒に対応の仕方を学びませんか」という呼びかけがなされています⁴ 。まさにその通りで、同じ苦境にある家族と繋がることで孤独感は和らぎ、建設的な対処法も見えてきます。問題をオープンにすることは恥ずかしいことでは決してありません。適切な支援を得るためにも、家族だけで問題を抱え込まないようにしましょう。
家族としてできる適切なサポート方法
では、家族は具体的にどのように関われば良いのでしょうか。ここからは家族が取るべき建設的な対応策を紹介します。ポイントは「本人に問題と向き合う責任を持たせつつ、回復への道筋を支える」ことです。以下のような方法が有効とされています。
- 病気への理解を深める: まず家族自身がギャンブル依存症について正しく理解することが重要です。依存症は本人の意思や性格だけの問題ではなく、様々な要因が重なって発症する「心の病気」です³ 。決して「家族の接し方が悪かったから」「本人がだらしないから」起きたわけではありません³ 。この病気は専門治療や支援によって回復が可能なものであり、意志の弱さや家庭の責任だけではないと知ることで、責める気持ちや罪悪感を和らげることができます。知識を持てば適切な対応もしやすくなりますので、自治体の啓発資料や専門書籍、信頼できるウェブサイトなどで情報収集すると良いでしょう。家族向けの講座やセミナーが開催されている地域もあります。
- 境界線とルールを設定する: 家族として支えるにあたっては、「ここまでは助けるが、ここから先は本人の責任」という明確な線引きをすることが大切です。例えば「借金の返済や生活費は本人が負担する」「嘘をついた場合は金銭的支援はしない」など、家族内でルールを決めて一貫して守ります² 。家族全員が同じ方針で対応することで、本人も自分の行動に責任を取らざるを得なくなります。甘い対応と厳しい対応が家族内で混在すると本人も混乱し、付け込む隙を与えてしまいかねません。話し合いにくい問題ではありますが、家族内でよく協議して対応方針を一致させておきましょう² 。そして決めたルールは情に流されて簡単に撤回しないことも重要です(「今回だけは…」と例外を作ると約束の効力が失われてしまいます)。毅然とした態度は本人に「家族にももう頼れない」と自覚させ、自立に向けた動機付けにも繋がります。
- 冷静で開かれたコミュニケーション: 本人と向き合う際は、できるだけ感情的にならず冷静に接するよう努めましょう¹ 。ギャンブル問題が発覚した直後など家族側が激しく動揺しているときに話し合おうとしても、どうしても非難口調になったり怒りがぶつけてしまいがちです。それでは本人は心を閉ざしてしまいます。まずは家族側が落ち着いて、伝えるべきことを整理してから話し合いの場を持つようにしましょう。話す際も「あなたのせいで迷惑だ!」ではなく「あなたのことが心配」「このままだとあなたがもっと苦しむことになる」といった気持ちを伝えるよう心がけます。責められていると感じさせずに心配している旨を伝えることで、本人も防衛的にならずこちらの話に耳を傾けやすくなります¹ 。また、日頃からギャンブル以外の何気ない会話も含め、「何でも話せる雰囲気づくり」をしておくことも大切です¹ 。コミュニケーションが断絶してしまうと支援の糸口もつかめなくなるため、家族として対話の扉は常に開けておくイメージで接しましょう。
- 専門の治療・相談につなげる: ギャンブル依存症からの回復には、本人が専門的な治療や支援を受けることが望ましいです。家族がいくら頑張って支えようとしても、専門知識や客観的視点なしに問題を解決するのは容易ではありません。そこで、精神科・依存症専門医療機関や相談機関への受診を強く促しましょう¹ 。例えば「〇〇病院の依存症外来に一緒に行ってみない?」と具体的な提案をすると動機付けにつながりやすくなります。借金問題で苦しんでいる場合も、まずは借金そのものよりギャンブル依存症の治療・回復に取り組むことが先決だと専門家は指摘しています⁵ 。専門機関では医師の診断やカウンセリング、認知行動療法など本人に合ったプログラムで対処してくれますし、依存症専門の回復施設やリハビリプログラム(外来・入院)もあります。なお本人が「自分は病気じゃない」「病院なんか行きたくない」と拒否するケースも多いです⁵ 。無理に連れて行こうとしても逆効果な場合、家族だけでも先に専門機関に相談してみることをおすすめします⁵ 。各都道府県の精神保健福祉センターや保健所には依存症相談の窓口があり、家族だけでも事情を聞いてアドバイスしてもらえます¹ 。専門家に相談する中で、本人を治療につなげるヒントが得られるかもしれません。まずは家族が情報収集と作戦会議をするつもりで、一度専門相談を利用してみてください。
- 家族自身の生活と心を守る: 忘れてはならないのは、サポートする家族自身も自分の人生を大切にするということです。家族が疲弊し、心身に不調をきたしてしまっては元も子もありません。趣味や仕事、他の家族・友人との時間を持つなど、「あなた自身の生活」を取り戻すことも並行して意識してください。最初は罪悪感を覚えるかもしれませんが、決して冷たいわけではなく長期戦に備えて英気を養うことが目的です。例えば意識的にリラックスできる時間を作ったり、必要であれば心療内科やカウンセラーに家族自身が相談してみるのも良いでしょう。場合によっては、一時的に物理的距離を取る(別居や実家に帰る等)ことが双方にとってプラスになることもあります。家族もまた支援を受けていい存在です。あなた自身の心のケアをおろそかにしないでください。それが結果的に本人の回復支援を長く続ける力にもなります。
専門機関や家族会(自助グループ)の活用方法
ギャンブル依存症の問題に対処するには、家族だけで頑張り過ぎず外部の力を上手に借りることが重要です。専門の相談機関や家族向けの自助グループ(家族会)など、利用できるリソースは積極的に活用しましょう。
● 専門家への相談: 前述の通り、各地の精神保健福祉センターや依存症専門医療機関では、ギャンブル問題に関する相談を受け付けています。家族からの相談も歓迎されていますので、「こんなことで相談して迷惑では…」と遠慮せずに連絡してみてください。専門家に話すことで状況を客観視でき、適切なアドバイスや情報を得られます。必要に応じて法律相談(借金問題であれば弁護士や司法書士)や経済的支援制度の紹介を受けることもできますし、本人を治療につなげるための具体策についても一緒に考えてもらえます。公的機関の相談は無料で匿名でも利用できますので、早めにアクセスしてみましょう。
● 家族向け自助グループへの参加: 同じ悩みを持つ家族同士が集まり、経験や気持ちを分かち合う場として自助グループ(家族会)があります。代表的なものに「ギャマノン(Gam-Anon)」があります。ギャマノンはギャンブル依存症者の家族・友人のための自助グループです⁵ 。全国各地で定期的にミーティング(集会)が開かれており、参加費は無料、原則として匿名でプライバシーは守られます。そこでは家族が自分の気持ちを自由に話し、他のメンバーの体験談に耳を傾けます。「同じ苦しみを経験した仲間」に出会えることで、張り詰めていた心がふっと軽くなることも多いですし、先に問題を乗り越えてきたメンバーから実践的なアドバイスをもらえることもあります⁵ 。また、長年ギャマノンに通い続けて自分の人生を取り戻した家族の姿を見ることで「自分も前向きに変われるかもしれない」という希望が湧いてくるでしょう。自助グループへの参加により家族自身が変わっていくと、結果として依存症の本人がその影響を受けて良い方向に向かうケースも多く報告されています⁵ 。まさに家族会は家族の回復と本人の回復、双方に良い効果をもたらす場なのです。
日本にはギャマノンの他にも、NPO法人が運営する家族会や地域の家族教室など複数の集まりがあります。例えば「全国ギャンブル依存症家族の会」⁴ は各都道府県で定期的に家族会を開催しており、公式サイトから参加方法や日程を知ることができます。自助グループは敷居が高いと感じるかもしれませんが、「自分だけじゃない」と思えるだけでも心が救われます。最初は聞いているだけでも構いません。同じ境遇の人たちの輪の中に身を置いてみることで、必ず得られるものがあるはずです。
● 家族カウンセリング・教育プログラムの利用: 医療機関や専門施設によっては、家族向けのカウンセリングや教育プログラムを提供している場合もあります。これは家族がプロのカウンセラーや治療者から直接アドバイスを受けられる場です。家族自身のメンタルケアと同時に、より良い対応方法(コミュニケーションの取り方、境界設定の仕方など)を学ぶことができます。例えば、認知行動療法に基づいたCRAFT(コミュニティ強化アプローチ家族トレーニング)というプログラムでは、家族が適切な関わり方を身につけることで本人の治療動機を高める効果が報告されています。こういったプログラムは専門のクリニックや支援施設で行われていますので、関心があれば相談機関で紹介してもらうと良いでしょう。
よくある質問と相談Q&A
最後に、ギャンブル依存症の家族から寄せられるよくある質問や相談事例を取り上げ、それぞれに対する回答とアドバイスを示します。同じ疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
- Q1. ギャンブル依存は家族(私)の育て方や環境が原因でしょうか?私のせいですか?
A. いいえ、家族のせいではありません。ギャンブル依存症は本人の意志の弱さや家族の努力不足によるものではなく、ストレス耐性や孤独感など様々な要因が重なって起きる複合的な問題です³ 。専門家も「本人の意志や周囲の努力の問題ではなく、適切な医療や支援によって回復し得る病気だ」と強調しています³ 。ご家族としては「自分にも責任があるのでは」と自責の念に駆られるかもしれません。しかし、過度に自分を責める必要はありませんし、そのような罪悪感はかえって今後の適切な対応の妨げになってしまいます。大切なのは過去よりも「これから何ができるか」です。どうかご自身を責めずに、前向きに対処法を学んでいきましょう。 - Q2. 借金の督促状が来ています。家族である私が代わりに返済すべきでしょうか?
A. 代わりに返済することはおすすめできません。 前述のとおり、借金の肩代わりは問題の先送りや再燃に繋がります² 。専門家も「一番大切なのは、本人の代わりに借金を支払わないこと」と強くアドバイスしています⁵ 。ご家族が連帯保証人になっていない借金であれば、法律上返済義務は本人にしかありません。本人にとって借金問題は自ら招いた重大な結果であり、まずはその現実に直面させることが必要です。苦しい状況を見るに見かねて助けてあげたくなるお気持ちはもっともですが、ここは心を鬼にして「自分で返済の道筋をつけさせる」ようにしましょう。どうしても心配な場合は、専門家(弁護士や多重債務相談窓口)に相談しつつ見守る形でも構いません。大切なのは本人に責任を取らせることです。家族が手を出さないことで初めて、本人は借金という現実と向き合い「もう二度と繰り返さないためにはどうすればいいか」を真剣に考えるようになります。 - Q3. お金を渡さないと、怒って物を壊したり暴力を振るわれそうで怖いです。どうしたらいいですか?
A. まずはご自身の安全を確保してください。 もし暴力や脅しがエスカレートして危険を感じる場合、一時的にでも安全な場所へ避難することが最優先です⁵ 。例えば近くのビジネスホテルや親戚宅に身を寄せる、場合によっては警察や配偶者暴力相談支援センターに相談して保護してもらうなども選択肢です。決して暴力に耐え続ける必要はありませんし、「家族だから見捨ててはいけない」などと考える必要もありません。あなたの身に危害が及ぶ状況では、一度物理的距離を取ってください。その上で、落ち着いてから専門の相談機関に事情を説明しましょう⁵ 。暴力の問題はギャンブル依存症とは切り離して対処すべき深刻な問題です。必要なら警察沙汰も辞さない覚悟で、毅然と対応してください。安全が確保できて初めて、経済的・精神的な問題にも取り組むことができます。 - Q4. 本人が「自分は病気じゃない」「恥ずかしいから病院には行きたくない」と治療や相談を拒否します。どうすればいいですか?
A. 依存症では「否認」が非常に強いことが多く、本人自ら助けを求めるケースは少ないと言われています⁵ 。無理に連れて行こうとしても逆効果になることもあります。このような場合、家族だけでも先に専門機関に相談することを検討してください⁵ 。家族が専門家に相談するのは決しておかしなことではなく、むしろ推奨されています。専門家に状況を話す中で、本人に受診を促すための具体的アドバイスをもらえたり、適切なタイミングや声掛けの方法について指南してもらえるでしょう。また、普段の会話の中で徐々に働きかけることも大切です。一度に説得しようとせず、「最近眠れないみたいだけど心配だな」「相談できる人がいると違うらしいよ」などと繰り返し優しく伝え、本人が「行ってみようかな」と思えるきっかけ作りを粘り強く続けてください。どうしても拒否が続く場合は、家族側が先に自助グループ(後述)に参加し、他の家族の体験談からヒントを得るのも有効です。本人が頑なでも家族が変われば状況が動くこともあります⁵ 。決して諦めず、できる準備を整えながら好機を待ちましょう。 - Q5. 家族の私まで自助グループ(家族会)に通う必要がありますか?本人が行くべきでは?
A. ご家族も是非、自助グループに参加することをおすすめします。 最初は戸惑うかもしれませんが、家族が変わることで本人の回復につながるケースは少なくありません⁵ 。ギャンブル依存症の問題は家族と本人が一体となって絡み合っていることが多く、家族側にも「共依存」と呼ばれる状態が生じがちです⁵ 。共依存とは家族が本人にのめり込みすぎて、自分自身を犠牲にしてでも世話を焼いたりコントロールしようとしてしまう状態です⁵ 。それでは前述したように良い結果を生みません。自助グループでは、そうした共依存から抜け出し「自分の人生を生き直す」ための学びが得られます。同じ境遇の仲間からの共感や励ましは、家族の心を癒やし前向きな変化をもたらしてくれるでしょう。家族が健康的に変わっていけば、不思議なことに本人にも良い影響が伝わるものです。実際、自助グループに通い始めた家族が境界線の引き方や接し方を学ぶうちに、結果として本人が自ら回復に向かうようになったケースも報告されています⁵ 。本人に治療の意思がなくても家族からできるアプローチはあります。その一つが家族自身の自助グループ参加なのです。「本人が行かないのになぜ私が…」と思わず、騙されたと思って一度参加してみてください。きっと心に響くものがあるはずです。 - Q6. ギャンブル依存症は本当に治せるのでしょうか?一生このままですか?
A. 適切な治療と支援を受ければ、ギャンブル依存症からの回復は十分に可能です。 実際、ギャンブルを長年断ち続け社会生活を取り戻している元当事者も数多く存在します。専門家によれば「ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分可能だ」とされています⁷ 。ただし、回復までの道のりは平坦ではありません。一度やめてもストレスや誘惑で再発してしまう(スリップ)ことも珍しくないのが現実です。それでも決して諦めないでください。再発してもすぐに治療や自助グループに戻ることで、少しずつギャンブルと無縁の期間が延びていきます。まるで禁煙や糖尿病の治療のように、「やめ続ける」こと自体が長期的なチャレンジなのです¹ 。家族としても、今日明日で劇的に良くならないからといって失望しないでください。焦らず見守り、良い変化があれば大いに称賛し、失敗があっても責めずに励まし、長い目で回復を支えていく姿勢が何より大切です。ギャンブル依存症は適切な支援の下で必ず改善できる病気です⁷ 。希望を持って、一緒に一日一日を積み重ねていきましょう。
まとめ
ギャンブル依存症の問題に直面した家族は、計り知れない苦労と悲しみを抱えていることと思います。本記事で述べたように、まずは間違った対応(経済的な肩代わりや過度の干渉など)を避け、本人に責任を自覚させつつ寄り添うことが重要です。その上で、専門機関や家族会など外部のサポートを活用し、家族自身もケアしていくことが求められます。状況が暗礁に乗り上げたように感じても、決して希望を捨てないでください。適切な対応を続ければ、少しずつでも前進できます。最後に改めてお伝えしますが、あなたは一人ではありません。 どうか周囲の支援を受けながら、ご自身の人生と大切な家族の回復に向けて歩み続けてください。