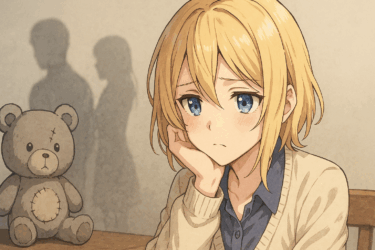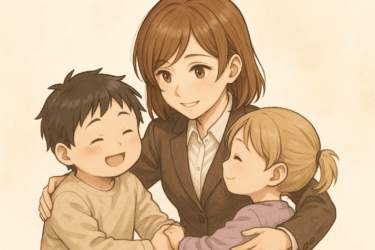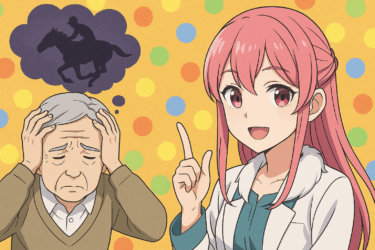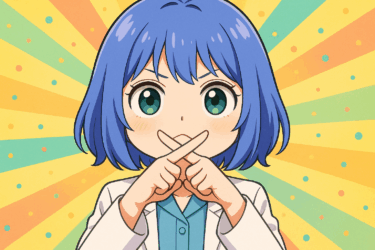はじめに
ギャンブル依存症(ギャンブル障害)は、本人だけでなく家族全体を巻き込む「家族の病」とも言われます 。配偶者や親は、最愛の人がギャンブルにのめり込み生活が破綻していく様子に直面し、怒りや混乱、裏切られた思いに打ちひしがれるでしょう。家族は借金や嘘に振り回され、心身ともに疲弊しがちです。一方で、「自分が何とかしなければ」と必死に問題解決に奔走するあまり、自分自身も共依存(コードペンデンシー)の状態に陥ってしまうケースも多く報告されています 。本記事では、ギャンブル依存症に向き合う家族(特に配偶者や親)が自立し、健全な生活を取り戻すためのステップと心構えについて、エビデンスに基づき解説します。
共依存と感情的なもつれとは
まず押さえておきたいのが共依存(コードペンデンシー)の概念です。元々はアルコール依存症者の配偶者に見られる状態を指す言葉で、アルコールに囚われる本人と同様に、家族が「本人を何とかしようとすること」に囚われて自己を見失った状態を意味しました 。つまり、他者(この場合ギャンブル依存の本人)の問題に過度に巻き込まれ、相手以上に必死で問題解決に取り組もうとし、自分のニーズや感情を後回しにしてしまう関係性を指します 。家族としては愛情ゆえに「助けたい」「支えたい」という気持ちで行動しますが、その裏には見捨てられる不安や罪悪感があり、知らず知らずのうちに有害な感情的なもつれ(縺れ)に陥ってしまうのです。
共依存状態の典型的な特徴として、専門家は「外向き志向(相手の問題ばかりに焦点が向く)、自己犠牲、相手の行動をコントロールしようとする試み、自分の感情の抑圧」が挙げられると指摘しています 。実際、ギャンブル問題を抱える人の家族には、借金の肩代わりや嘘の後始末などで「問題解決者」役を買って出たり、本人の機嫌を損ねないように自分の本音や怒りを押し殺したりする行動パターンがよく見られます。こうした共依存の悪循環に陥ると、家族自身も極度のストレスと自己喪失を抱え、結果的に問題を長引かせる要因になりかねません。
しかし大切なのは、家族は本人の問題を「発生させた」わけでも「治せる」わけでもないという現実です 。ギャンブル依存症は脳の報酬系の変化によって生じる病であり 、家族がどれほど愛情や努力を注いでも、それだけで完治させることはできません。この事実を理解しないまま家族だけで問題を抱え込むと、共倒れになってしまう恐れがあります。まずは自分も「病気の影響を受けた当事者」であること、自分自身の回復も必要であることを自覚することが、第一歩となるのです。
自助グループに学ぶ原則:ギャマノンの知恵
Gam-Anon(ギャマノン)は、ギャンブラーズ・アノニマス(GA、ギャンブル依存症本人の自助グループ)の姉妹プログラムとして、家族や友人を支援するために生まれた自助グループです。アルコール依存症者の家族の自助グループ(Al-Anon)と同様に12ステップのプログラムを基盤とし、世界各地でミーティングが行われています。日本でも1989年に発足し、各地に家族会が存在します。
ギャマノンやその他の家族会では、「あなた一人ではない。私たちもかつて絶望し、恐れ、途方に暮れていました。しかしギャマノンを通じて、愛する人がギャンブルを続けていようといまいと、自分自身の正常な考え方と生活を取り戻す道が見つかりました」 というメッセージが共有されています。これは、家族自身が自分の人生を取り戻すことに焦点を当てる大切さを説くものです。ギャマノンの原則から学べるポイントをいくつか紹介します:
- 「3つのC」への気づき: アルコール依存症の家族支援で知られる合言葉に「Cause, Control, Cure」の3Cがあります。すなわち「あなた(家族)はそれを引き起こした(Cause)わけではなく、コントロール(Control)もできず、治す(Cure)こともできない」という真実です 。ギャンブル依存症でも同様で、家族がまずこの事実を受け入れることが重要です。問題を自分のせいと感じている配偶者は少なくありませんが、その罪悪感から解放されることが回復の出発点となります。
- 依存症を「本人の病気」と切り離す: ギャマノンでは、「病気と本人そのものを分けて考える」ことが勧められます。つまり、ギャンブルに向かわせる衝動は病的な症状であり、本人の人間性の問題ではないと理解するのです。この視点は、家族が責めや怒りの感情に振り回されず、冷静に対応策を考える助けになります。また、「愛があればやめられるはず」という考えを捨てることにもつながります。実際、ギャンブル依存症者が家族を愛していても自力でやめることは困難であり、それを家族が責めても逆効果なのです。
- 自分の人生に焦点を戻す: 共依存から抜け出すための最大のポイントは、「他人の問題」と「自分自身」を切り離し 、自分の健康や幸せに目を向け直すことです。ギャマノンではしばしば「Detach with love(愛情を持って距離を置く)」という言葉が使われます。これは冷たく突き放すのではなく、相手の人生の責任を本人に返し、自分は自分の人生を生きるという宣言です。例えば家族会では「どうか本人を手放してください。そして自分らしく生きてください」というメッセージが繰り返し強調されます。経済的・精神的に相手に巻き込まれた状態から一歩離れることで、家族自身が健康を取り戻すだけでなく、結果的に本人が自ら問題に向き合うきっかけにもなり得ます。
- 仲間とつながる: 家族だけで抱え込まないこともギャマノンの重要な教えです。同じ立場の人が集まるミーティング(家族会)に参加すれば、体験を「話し」、人の話を「聞く」中で知識や勇気、安心感を得られます。家族会はアドバイスの場ではなく、互いの思いを安心して語り共有する場です。自分だけが苦しいのではないと知るだけでも心は軽くなりますし、先ゆく仲間の体験からヒントを得ることもできます。また必要に応じて専門のカウンセリングを受けるのも有効です 。専門家や支援者に気持ちを打ち明けることで、自身の感情整理や客観的な視点の獲得につながります。
家族の心理的回復ステージ
ギャンブル依存症の家族が自立への道を歩み始める過程では、心理的にいくつかの段階を経るとされています。すべての人に当てはまるわけではありませんが、多くの家族が経験する共通のステージとして、以下のような流れが報告されています。
- ショックと否認: 最初にギャンブル問題が発覚した時、多くの家族は強いショックを受けます。「まさか自分の夫(妻・子)が…」という信じられない気持ちや、怒り、動揺で心が乱されるでしょう。恥ずかしさから他人に相談できず、問題を隠そうとする傾向もあります。しかし否認や隠蔽は状況を悪化させるだけです。まずは起きている事実を直視し、自分の感じている怒りや悲しみを認めることが重要です。限界ギリギリまで頑張ってきた自分自身の疲れや傷つきにも気づきましょう。
- 罪悪感と自己非難: 問題を認め始めると、今度は「自分の育て方が悪かったのか」「配偶者として至らなかったのでは」といった罪悪感に苛まれることがあります。また周囲から責められているように感じる人もいます。しかし繰り返しになりますが、依存症は誰かの性格や育て方が直接の原因で起こるものではなく、「誰のせいでもなく病気のせい」なのです。ここを履き違えると、罪悪感ゆえに問題行動を許容してしまったり、適切な対処が取れなくなってしまいます。罪悪感を手放すためには、依存症について正しい知識を学ぶことが有効です。専門書やセミナー、自助グループで得た知識によって「自分のせいではない」と腑に落ちれば、必要以上に自分を責める悪循環から抜け出せるでしょう。
- コントロールしようとする試み: 家族として何とか事態を改善しようと、本人の行動を管理・干渉し始める段階です。金銭管理を引き受けたり、付き添ってギャンブルをさせないよう監視したり、借金の申し出に対応したりと、まさに「消火係」として奔走します。一時的にうまくいくように見えても、根本的な解決にならないことがほとんどです。むしろ、家族が常に後始末をしてくれる状況は本人にとって都合が良く、問題を先延ばしにするだけになりかねません。この段階では家族も極度のストレスに晒され、「どうにかしなければ」という強迫観念と「もう疲れ切って無理だ」という無力感との板挟みになりやすいです。専門家は、この段階で一度立ち止まり「自分がどれほど影響を受けているか」「このままでは共倒れになってしまう」と自覚することが次のステップへの鍵だと指摘します。
- 感情的な分離(デタッチメント): 家族が限界を感じ、次第に「この問題は自分にはコントロールできない」と悟り始める段階です。これは諦めとは異なり、問題解決への執着を手放す受容の境地と言えます。具体的には、本人の意思決定や失敗も含め「本人の人生」として尊重し始めること、自分の人生との健全な境界を引き直すことが含まれます 。この過程ではしばしば心の葛藤がありますが、共依存の悪循環から抜け出す重要なターニングポイントです。ギャマノンでいう「愛情を持って突き放す」姿勢を取り入れ、「私はあなたを愛しているからこそ、あなた自身の力で問題に向き合ってほしい。私はもうあなたのギャンブルの責任は負いません」と心に決めます。家族にとっては勇気のいるプロセスですが、研究によれば家族が共依存を手放すと当事者(ギャンブラー)が回復に向かうことがある程度確認されています 。実際に、あるギャンブル依存症者の妻は家を出て距離を置いたところ、半年で夫に劇的な変化が見られたと報告しています 。このように家族側が変わることで本人にも変化が及ぶケースは珍しくありません。
- 自己への集中と成長: 問題から一歩離れることに成功すると、今度は空いたエネルギーを自分自身の人生に向けられるようになります 。趣味や仕事、人間関係など、長らく後回しにしてきた自分の大切なものを取り戻す段階です。心理的にも少しずつ安定を取り戻し、「自分は自分、相手は相手」という境界意識が芽生えてきます 。また、自助グループでの活動やカウンセリング継続を通じて、自らのコミュニケーションの癖や生い立ちで形成された価値観を見つめ直し、今後の人生をより良くするための学びを深めていく人もいます。これは家族にとっての回復であり、新たな成長のステージと言えるでしょう 。「自分の人生を自分らしく生きてよいのだ」と実感できたとき、家族はギャンブル問題に以前ほど振り回されなくなり、必要に応じて冷静にサポートできる真の意味での「自立」を達成します。
境界を引き直す:エンエイブル(養護的な関わり)をやめる実践ステップ
上記の回復ステージの中で特に重要なのが、4~5の段階にあたる境界の再構築とエンエイブル(Enabling:結果的に問題行動を助長してしまう関わり)の停止です。具体的に家族はどんな行動を取れば良いのでしょうか。以下に、専門家や自助グループで推奨される実践的ステップをまとめます。
- 金銭的支援を断つ: もっとも重要なのはお金の貸し借りをしないことです。どんなに切羽詰まった様子で頼まれても、ギャンブル絡みの借金を肩代わりしたり、遊ぶお金を渡したりしてはいけません。借金問題の尻拭いを家族が引き受けてしまうと、本人は深刻さを実感できず、かえって依存を長引かせる結果になります。経済的な苦境は本人自身が向き合うべき問題です。苦しくても「自分で専門機関に相談してごらん」と突き放す勇気を持ちましょう。
- 自然な結果と責任を本人に返す: 家族が先回りして火消しをするのではなく、本人がギャンブルの結果生じた現実(未払いの請求書や人間関係のトラブル等)に直面する機会を奪わないことも大切です。例えば、督促状を隠さず本人に渡す、嘘の言い訳づくりに協力しない、といった対応です。「あなたの問題はあなた自身で処理してね」と穏やかに告げ、責任を本人に返しましょう。ただし暴力など危険が及ぶ場合は直ちに安全確保を最優先してください。
- 許容範囲とルールを明確に伝える: 家族としてどこまでサポートし、何を許容できないのか、境界線を具体的に言葉で示すことも必要です。たとえば「我が家では借金はこれ以上しないこと」「生活費には手を付けないこと」「約束を破ったら◯◯します(実家に戻ります等)」といったルールを決め、相手に伝えます。伝える際は感情的に責め立てるのではなく、あくまで冷静に愛情と率直さを込めて伝えましょう。例えば「あなたが大切だからこそ、私はもうあなたの借金を肩代わりしません。これはあなた自身の問題だからです」といった言い方です。専門家は「毅然としかし優しく(firm but kind)」境界を伝えることを推奨しています。
- 期待しすぎない: 一度境界を伝えたからと言って、すぐに本人が変わるとは限りません。何度も裏切られ、「口先だけの約束」に失望することもあるでしょう。しかしその度に怒りや説教で相手を責め立てても逆効果です。境界線を守ることは家族にとっても苦しい作業ですが、相手が変わることを過度に期待せず、「自分の決めた対応を一貫して続ける」ことにフォーカスしましょう。時間がかかっても、家族が態度を変え一線を引いたことは必ず本人に伝わっています。実際、家族側が対応を改めたことで、後になって本人が「あの時見放されて目が覚めた」と語る例もあります 。
- 自分自身の生活と感情を大事にする: 境界設定と並行して忘れてはならないのが、家族自身のセルフケアです。長期間ストレスに晒されてきた心と体を癒やす時間を意識的に作りましょう。十分な睡眠や食事、趣味の時間、信頼できる友人とのおしゃべりなど、「自分がほっとできること」「楽しいと感じられること」に取り組むことは決してわがままではありません。それは家族が生き延びるために必要な行動です。罪悪感を覚える必要はなく、家族が元気になること自体が間接的に本人のためにもなるのです。また、迷いや不安が生じたら一人で抱え込まず、専門の相談機関や自助グループに助けを求め続けましょう。「家族会に通いながら実践してみてください」という言葉通り、家族の対応は一朝一夕に変えられるものではありません。仲間と支え合いながら少しずつ取り組めば良いのです。
以上のようなステップを踏むことで、家族は依存症者との間に健康的な境界を引き直し、自分自身の生活を立て直すことができます。専門家のレビューによれば、パートナーによる適切な境界設定と支援は依存症からの回復を妨げるどころか、むしろ回復を後押しする効果があるといいます 。実際、ギャンブル依存症治療においても家族の関与は治療継続率や成果を向上させるとの報告があり 、家族自身が元気になることは「WIN-WIN」だと言えるでしょう。
声かけ例:伝えるべき言葉・避けるべき言葉
家族が自立に向けて行動を起こす際、本人への声かけも重要です。ここでは、専門家の助言や自助グループの経験談に基づき、「こんな風に伝えてみよう」という例と、「これは避けた方が良い」というNG例を紹介します。
前向きな声かけの例
- 「私はあなたのことをとても心配しています」 – 主語を「私」にして、自分の気持ちとして伝えることがポイントです。「あなたはギャンブルで家族を苦しめている!」と非難するのではなく、「私は~と感じている」と伝えることで、相手も防衛的になりにくくなります。例えば「私は、あなたのギャンブルがあなた自身と家族に与えている影響がとても心配です」と切り出せば、相手も耳を傾けやすいでしょう。
- 「あなたには専門家の助けが必要だと思います」 – 問題の深刻さに気づいてもらうために、治療やカウンセリングの提案をしてみましょう。「意志が弱いからやめられないんだ」ではなく、「病気だからプロの助けが有効なんだ」というニュアンスで伝えます。「一緒に相談に行ってみない?」と寄り添う姿勢を見せるのも良い方法です。
- 「あなたを支えたいけれど、あなたのギャンブルは支援できません」 – 境界を伝えるフレーズです。例えば「私はあなたのことを大切に思っています。だからこそ、借金の肩代わりはもうできません。あなた自身で解決してほしいの」といった表現です。「愛しているからこそNoと言う」の姿勢を明確にしましょう。このように問題行動と人間としての価値を切り分けて伝えることが大切です。
- 「私も勉強中です。一緒に少しずつ変わっていきたいです」 – 家族自身も対応を学び、回復していく途中であることを正直に伝えるのも効果的です。「私も専門家に相談して対応を学んでいるところです」などと言えば、相手もプレッシャーを感じにくくなりますし、あなたが本気で向き合っている姿勢が伝わります。互いに「より良く変わるために頑張ろう」という前向きな空気を作ることができます。
避けるべき言葉の例
- 「本当に家族を愛しているならやめられるはず」 – 愛情や根性の問題にすり替えて責める言葉は逆効果です。本人もやめられない自分に自己嫌悪を感じている場合が多く、追い打ちをかけると開き直りやさらなる隠蔽につながります。
- 「また裏切ったのね。もうあなたなんて信用しない」 – 裏切られた怒りから出てしまいがちですが、感情的な糾弾は建設的な解決を遠ざけます。信用できない気持ちは当然ですが、「どうせまた嘘をつくんでしょ」と突き放すような言い方は避けましょう。代わりに「約束が守れない状況が続いてとても残念です」と自分の感情として伝える方が冷静な対話につながります。
- 「もう二度とギャンブルしないって約束できる?」 – 今の段階で本人に絶対の約束をさせようとするのは現実的ではありません。依存症のコントロールは本人にも難しく、「二度としません」と言えてしまう人ほどむしろ信用できないとも言われます。軽々しい約束より、具体的な行動計画(専門治療に行く等)を話し合う方が有益です。
- 「あなたは意志が弱い/恥ずかしい人間だ」 – 人格を否定するレッテル貼りや恥の感情を煽る発言は厳禁です。依存症者は既に自己肯定感が低下している場合が多く 、羞恥心や劣等感は逆にストレスとなってギャンブル衝動を掻き立てる恐れもあります 。非難ではなく問題行動そのものに焦点を当て、「あなた自身は大切だが、その行動は受け入れられない」という伝え方を心がけましょう。
家族関係の明暗:事例から見る教訓
最後に、実際の家族の動き方によってどのように結末が変わり得るか、典型的なケースを2つ考えてみます。(注:プライバシー保護のため事例は架空のものですが、臨床でよくあるパターンをモデルにしています。)
ケース1: 増長する依存 – 「どこで間違えたのか」
佐藤さん(仮名)の夫はパチンコにのめり込み、消費者金融から多額の借金を抱えるようになりました。佐藤さんは夫を信じ、「今回だけは…」と幾度も借金を肩代わりして返済しました。夫が嘘をつくたびに激しく責めましたが、結局は情にほだされて許し、家計から穴埋めしてしまいます。夫は改心するどころか次第に借金額を増やし、ついには家のローンまで滞納する事態に…。限界を迎えた佐藤さんは、「私が支えなければこの人は破滅する」との思い込みから離れられず、自らの趣味や友人関係も絶って夫につききりになりました。心身ともに疲れ果て鬱状態になった彼女は、周囲からの助言でようやく家族会に足を運びます。そこで初めて「自分自身が共依存の泥沼にはまり、夫の問題行動を無意識に助長していた」ことに気づき、愕然としました。
解説: このケースでは、佐藤さんの行動が典型的な**エンエイブル(問題行動の容認・補強)**となってしまっています。借金の肩代わりや度重なる許しは、一見夫を救っているようでいて実は夫から問題の深刻さを実感する機会を奪っていました。本人が痛みを感じなければ「まだ大丈夫だ」と錯覚し、ギャンブルを続けてしまいます。佐藤さん自身も夫に振り回されるあまり視野が狭くなり、うつ症状が出るまで自己犠牲を続けてしまいました。これはまさに共依存の悪循環です 。幸い彼女は支援団体に繋がり、自分の生き方を見直す契機を得られましたが、もしそのまま孤立していたら、夫は破滅的な結末を迎え、佐藤さんも心身を病んでいた可能性があります。専門家によると、家族が共依存状態に留まっている限り、依存症本人の回復も進みにくいとされます 。まさに「共倒れ」の危険性をはらんだパターンと言えるでしょう。
ケース2: 境界設定による好転 – 「それぞれの回復」
一方、田中さん(仮名)のケースでは異なる展開を辿りました。田中さんの妻はオンライン賭博にのめり込み、借金を隠していました。事実を知った田中さんは激怒しましたが、家族会で得た知識を活かし冷静に対応することにしました。彼は妻に対し、「あなたのことは愛しているし支えたい。でも借金の清算は自分でやってほしい」と伝え、専門の相談窓口情報を渡しました。以降、二度とお金は貸さないと宣言し、実行しました。また、妻が嘘をついたときも頭ごなしに責めるのでなく、「今日は話したくない」と静かに距離を置き、自分自身はジム通いや友人との交流を再開しました。最初は逆上していた妻も、自分の給料で借金を返済する苦労を経験する中で次第に現実と向き合い始めました。半年後、妻は自ら「カウンセリングを受けてみる」と切り出し、専門治療につながりました。今では夫婦でそれぞれ自助グループに通い、再発防止と信頼回復に取り組んでいます。田中さんは「あのとき妻と適度な距離を置いたことで、お互いに自分を取り戻せた」と振り返っています。
解説: 田中さんの行動は、家族として模範的な境界設定と非エンエイブルの実践と言えます。彼は妻の借金問題を本人の責任として扱い、経済的な支援を断ちつつ、しかし決して見放すのではなく精神的サポートの意思は示しました。これはまさに「毅然としかし愛情を持って」接する態度であり、妻に現実を直視させる効果がありました。加えて、田中さん自身が自分の生活を取り戻そうと動いたことで、夫婦それぞれが冷静になる時間が生まれました。専門家の研究でも、家族が共依存を手放し自分の人生に焦点を当て始めると、当事者の自尊心回復にも良い影響を与えると報告されています。このケースでは、家族と本人がそれぞれ並行して回復していく好循環が生まれました。もちろん全てのケースがこう上手く進むわけではありませんが、境界を引き直すことが家族と本人双方にプラスの変化をもたらす可能性を示しています。
おわりに
ギャンブル依存症の問題に直面した家族にとって、自分自身が回復し自立することは決して自己中心的な選択ではありません。それは家族全体の健全さを取り戻すために必要不可欠なプロセスです。共依存の連鎖を断ち切り、感情的なもつれから解放されることで、初めて見えてくる解決策もあります。家族が自立すれば、結果的に本人が問題に立ち向かう土壌が整うという側面も無視できません。実際、国際的なレビュー研究でも「家族の関与と支援はギャンブル依存症の治療アウトカムを向上させる」ことが指摘されています 。
困難な道のりかもしれませんが、決して孤独になる必要はありません。全国の家族会や専門機関では、同じ悩みを抱える人々や専門スタッフが手を差し伸べています。どうかあなた自身の人生を取り戻す一歩を踏み出してください。それは同時に、愛する人が立ち直る一歩にもつながっていくのです。
参考文献(参考資料):
- Calderwood, K. A., & Rajesparam, A. (2014). Applying the codependency concept to concerned significant others of problem gamblers: Words of caution. Journal of Gambling Issues, 29.
- Kourgiantakis, T., Saint-Jacques, M. C., & Tremblay, J. (2013). Problem gambling and families: A systematic review. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 13(4), 353–372.
- Rotunda, R. J., & Doman, K. (2001). Partner enabling of substance use disorders: Critical review and future directions. American Journal of Family Therapy, 29(4), 257–270.
- New York Council on Problem Gambling. (n.d.). Gam-Anon – Addiction support for family members and friends.
- Strength & Hope. (n.d.). Learn and remember the 3 C’s.