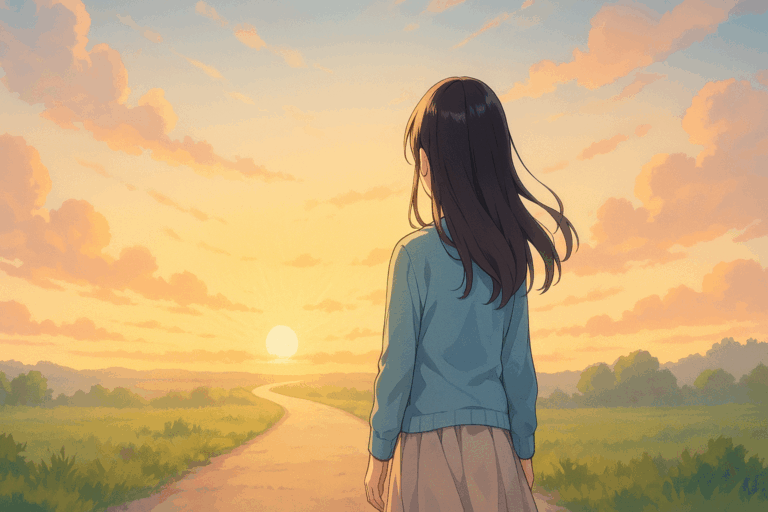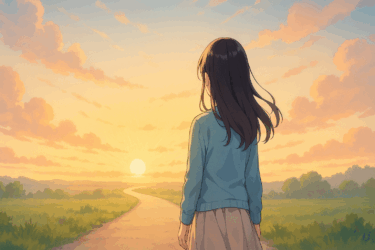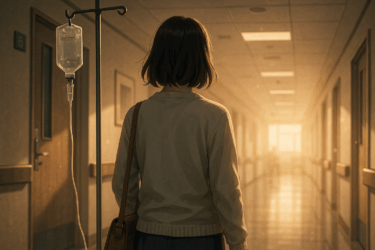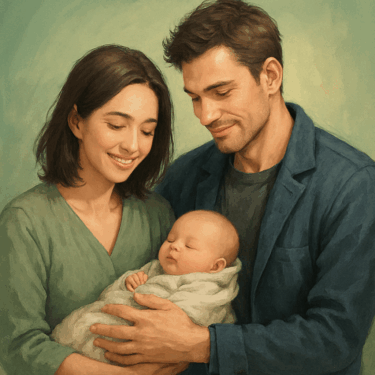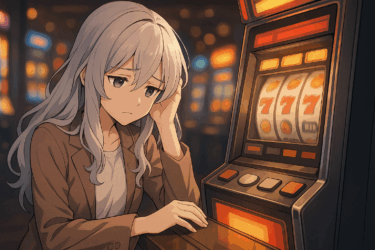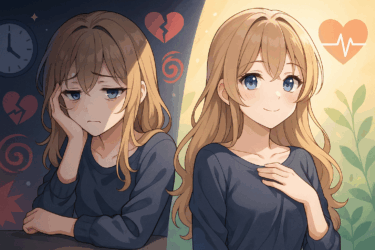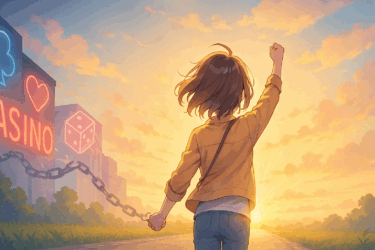ギャンブル依存症は、経済的破綻や人間関係の崩壊、自殺のリスクすら伴う深刻な問題です。しかし適切な治療と支援によって回復が十分に可能な疾患とされています。実際、厚生労働省の全国調査(2017年)では、日本の成人の約3.6%(推計約320万人)が生涯にギャンブル依存症に陥った経験があると報告されました。この数値は主要欧米諸国と比べても際立って高く、日本では28人に1人がギャンブル依存症の疑いがある計算です。このような状況から、「自分は意志が弱いだけ」と誤解されがちなギャンブル依存症について正しく理解し、国内外の支援プログラムを知ることは、当事者やご家族が回復への一歩を踏み出すために極めて重要です。もしあなたやあなたの大切な人がギャンブル依存症でお困りなら、一人で抱え込まないでください。本記事では、初心者にも分かりやすく、日本国内の代表的な回復支援制度と主要な海外(アメリカ・イギリス・オーストラリア等)のプログラムを比較しながら紹介します。適切な支援を受けることで、ギャンブル依存症は必ず回復へ向かいます。一緒に各種プログラムの特徴を見ていきましょう。
ギャンブル依存症の回復プログラムとは?
ギャンブル依存症の回復プログラムとは、ギャンブルから抜け出し正常な生活を取り戻すことを目的とした各種の治療・支援活動の総称です。具体的には、専門医療機関での治療プログラム、自助グループへの参加、認知行動療法によるカウンセリング、電話やオンラインによる相談サービス、そしてリハビリ施設での更生プログラムなどが含まれます。これらのプログラムは単独でも効果がありますが、組み合わせて利用することで相乗効果を発揮する場合も多いとされています。例えば「医療機関で治療を受けながら自助グループに参加する」ことで再発率をさらに下げられるとも言われています。ここから、日本国内と海外の主な回復支援策について、それぞれの特徴や効果を順に見ていきましょう。あなた自身やご家族に合った支援を見つけ、ぜひ積極的に活用してみてくださいね。
日本国内のギャンブル依存症回復支援制度
まずは日本国内で利用できる代表的な回復支援プログラムを紹介します。日本では近年、ギャンブル等依存症対策基本法の制定や政府の基本計画策定に伴い、治療体制や相談窓口の整備が進みつつあります。とはいえ「どんな支援があるのか分からない」「どこに相談すればいいのか不安」という方も多いでしょう。ここでは医療機関での専門治療、自助グループ、カウンセリング療法、電話・オンライン相談、回復施設といったカテゴリー別に、国内の支援内容を解説します。
医療機関での専門治療プログラム
ギャンブル依存症はれっきとした精神疾患であり、専門の治療プログラムがあります。精神科や依存症専門外来を持つ医療機関では、医師や臨床心理士による包括的な治療を受けることが可能です。具体的には、診察や精神療法(カウンセリング)、認知行動療法(CBT)、必要に応じた薬物療法などを組み合わせ、患者一人ひとりの状態に合わせたプログラムが提供されます。例えば国立病院機構久里浜医療センター(神奈川県)は国内有数の依存症治療拠点病院で、重症例には約9週間の入院治療プログラムを基本としています。入院中は心理教育や生活指導に加え、認知行動療法に基づくグループ療法、さらには怒りのコントロール訓練や社会生活技能訓練(SST)、作業療法など多角的なプログラムが実施されます。また必要に応じて借金問題への対処(弁護士相談の案内等)や、退院後の自助グループ(GA)参加支援まで組み込んでいる点が特徴です。
外来治療の場合は、基本的に定期通院による長期的なサポートが行われます。典型的な例では週1回の通院を1~2年程度継続し、医師の診察やカウンセリングを通じてギャンブル衝動のコントロールや生活習慣の改善を図ります。症状に応じて抗不安薬などが処方されることもあります。外来治療ではご本人の意欲と根気が重要ですが、専門スタッフが寄り添い再発防止まで伴走してくれます。また必要に応じてご家族もカウンセリングの対象となり、依存症への正しい理解や接し方について助言を受けられます。
医療機関での治療は公的医療保険が適用されるため、費用面のハードルも比較的低く抑えられています。通常は自己負担3割ですが、自治体によっては自立支援医療制度の適用で自己負担が1割に軽減される場合もあります。受診を検討する際は、まずお近くの精神科・心療内科に「依存症外来」があるか調べてみましょう。各都道府県には依存症治療拠点病院が指定されており、地域の精神保健福祉センターや保健所に相談すれば適切な医療機関を紹介してもらえます。治療はつらい道のりかもしれませんが、専門の医療チームと二人三脚で取り組むことで、ギャンブルをしない生活と健康な心身を取り戻すチャンスが生まれます。
自助グループ(ギャンブラーズ・アノニマス、ギャマノンなど)
自助グループ(セルフヘルプ・グループ)とは、同じ問題に直面している当事者やその家族が自主的に集まり、互いの体験や知恵を分かち合って支え合うピアサポートの場です。ギャンブル依存症の場合、代表的な当事者グループがギャンブラーズ・アノニマス(GA)であり、家族向けグループがギャマノン(Gam-Anon)です。GAは1957年にアメリカで誕生し、日本では1989年に最初のミーティングが開催されました。現在では日本全国46都道府県に約196のGAグループがあり、日々ミーティングが行われています(2020年2月時点)。一方、ギャマノンはギャンブル依存症者の家族・友人を対象にしたグループで、1960年にアメリカで始まり、日本では1991年から活動が開始されました。こちらも2020年時点で全国180か所以上にミーティング拠点が広がっています。
自助グループの活動では、メンバー同士が実名ではなくニックネームや匿名で参加し、自分の体験談や今の想いを語り合います。「同じ苦しみを分かってくれる仲間」と出会うことで、孤独感や罪悪感が和らぎ、「自分だけじゃないんだ」という安心感を得る人が多くいます。実際に仲間と経験や情報を分かち合うことで、気づきや癒し、そして希望や問題解決のヒントを得る参加者が数多く報告されています。専門家の指導ではなく当事者同士の対等な関係で運営されるため、失敗談も含めて本音で語り合える温かい雰囲気が特徴です。ミーティングでは「今日一日賭けずに過ごす」ことを目標に互いに励まし合い、ギャンブルをしない生き方を模索します。
参加方法もシンプルで、事前の予約や申し込みは不要です。各グループが定期開催するミーティング会場(多くは公共施設や会議室、教会の一室など)に決められた時間に行くだけで参加できます。初めて行くときは勇気がいるかもしれませんが、受付で「初めてです」と伝えればメンバーが親切に迎えてくれるので安心してください。参加費も一切かかりません(運営費はその場での任意のカンパで賄われています)。もちろん途中で話を強要されたり入会を迫られたりすることもなく、聞いているだけでも構いません。ギャンブルをやめたい本人であれば誰でもGAに参加でき、家族や友人であれば本人が同伴しなくても単独でギャマノンに参加できます。
自助グループの効果は研究でも認められており、継続的にミーティングに通うことでギャンブルをしない生活が安定しやすいとの報告もあります。また、専門治療と組み合わせることで再発防止効果が高まるとも指摘されています。何より、「自分のことを理解してくれる仲間がいる」という心の支えが、回復への大きなモチベーションとなるでしょう。孤独に戦うのではなく、ぜひ仲間の力を借りてみてください。全国のGAやギャマノンの開催場所・日時は公式サイトで確認できるほか、最寄りの精神保健福祉センターに問い合わせれば教えてもらえます。あなたは決して一人ではありません。同じ苦しみを乗り越えようとする仲間が全国にいます。扉を叩く勇気が、きっと新たな希望につながるはずです。
認知行動療法(CBT)によるカウンセリング
近年、認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)がギャンブル依存症の治療法として大きな注目を集めています。CBTとは、ギャンブルに走ってしまう考え方のクセ(認知の歪み)や感情のパターンに働きかけ、それを修正することで衝動的な賭博行為を抑制しようという心理療法です。具体的には、「どうせ負けたぶんを取り返せるはず」といった誤った信念を患者と一緒に検証し、現実的な思考に置き換えるトレーニングを行います。また、ギャンブルに誘発される状況(給料日やストレスを感じたとき等)を特定し、それらを回避したり健全な対処行動に置き換えたりするスキルも身につけます。セッションは通常、専門の臨床心理士による週1回程度の個別またはグループ面接で、数ヶ月にわたり継続します。途中で宿題(ギャンブル日記をつける等)が出されることもあり、患者自らが自分の行動パターンに気づき改善していけるようサポートします。
CBTの有効性は多数の研究で実証されており、ギャンブルへの衝動や頻度を有意に減少させることが報告されています。例えばあるメタ分析では、CBT介入によりギャンブル問題の重症度が大きく改善し(効果量g=−0.91)、ギャンブル実施頻度も減少したとされています。こうした科学的エビデンスから、CBTは「ギャンブル障害に対する最も効果的な治療法の一つ」と位置付けられています。実際、日本の専門医療機関でも入院・外来プログラムにCBTを組み込む例が増えており、久里浜医療センターでも認知行動療法をベースとした治療を提供しています。
対象者は治療意欲のあるギャンブル依存症当事者です。家族は直接の対象ではありませんが、必要に応じて家族向けの教育プログラムやカウンセリングが別途提供されることもあります。参加方法としては、依存症専門医療機関で医師の診察を受けた際に「CBTを受けてみたい」と相談するのが一般的です。院内で心理士によるCBT外来を紹介してもらえる場合や、院外のカウンセリング機関を案内してもらえる場合があります。また地域の精神保健福祉センターでも、認知行動療法に関する情報提供やカウンセラーの紹介を行っている所があります。
費用は医療機関内で実施される場合、保険診療の範囲で受けられることが多いです。一方、民間のカウンセリングルームで受ける場合は自費扱いとなり、1回あたり数千円~数万円程度の料金が発生します。ただし自治体によっては無料カウンセリング事業を行っているケースもありますので、経済的に難しい場合はお住まいの役所や保健センターに相談してみましょう。
認知行動療法によって「ギャンブルに頼らなくてもストレスに対処できる自分」を取り戻せたという声も多く聞かれます。「どうせ自分なんてまた賭けてしまう」という自己否定的な思考を、「自分にも変われる部分がある」と前向きに捉え直すことで、回復への道筋が見えてきます。専門家の伴走のもと、新しい思考と行動のパターンを身につけていきましょう。
電話・オンライン相談サービス
「いきなり病院やグループに行くのはハードルが高い…」という方にまず利用していただきたいのが、電話やインターネットによる無料相談サービスです。日本国内では、国や自治体、民間団体が運営する複数の相談窓口があり、匿名・無料で専門の相談員に悩みを打ち明けることができます。代表的な窓口としては、一般財団法人ギャンブル依存症予防回復支援センターの「サポートコール」(年中無休・24時間対応の全国共通ダイヤル)や、認定NPO法人リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)の相談電話(主にパチンコ・パチスロ依存が対象、平日10時~22時)などがあります。これらはいずれもフリーダイヤルで通話料も無料。相談員は依存症やカウンセリングの専門研修を積んだスタッフで、話を丁寧に傾聴し、状況に応じて適切な支援先を案内してくれます。電話だけでなくメールやウェブ相談フォームで受け付けている窓口もあり、特に昨今では24時間365日対応のオンラインチャット相談を提供する団体も出てきています。
電話・オンライン相談の大きなメリットは、思い立ったその場ですぐに専門家とつながれることです。ギャンブルで「もう限界だ」と感じた瞬間に電話をすれば、危機的状況を乗り越えるためのアドバイスや心の支えを即座に得られます。また、顔を合わせない分プライバシーが守られる安心感から、対面では言いづらい悩みも打ち明けやすいでしょう。「家族に知られず相談したい」「誰にも言えず一人で苦しい」という方にとって、まずこの匿名相談を利用することが問題解決への第一歩になります。
対象者はギャンブル問題に悩むご本人だけでなく、そのご家族や職場の同僚など周囲の支援者も含まれます。実際、窓口には「夫を助けたい」「息子が心配だ」という家族からの相談も多く寄せられています。相談員はそうした家族の不安にも寄り添い、「まずご自身ができる対処」を一緒に考えてくれます。例えば「借金の肩代わりは逆効果」「本人が自分で問題に向き合うのを支える」というアドバイスを受け、家族自身が冷静に対応できるようになるケースもあります。
費用は基本的に完全無料です。これらの相談窓口は公的資金や民間からの寄付で運営されており、利用者がお金の心配をする必要は全くありません。繰り返しになりますが、電話番号やメールアドレスさえ分かれば誰でもすぐに利用できます。消費者庁のサイトにも各種相談窓口の一覧がありますし、各都道府県の精神保健福祉センターや市町村の保健所でも地域の相談先を教えてもらえます。
「自分の問題を誰かに話す」ことは大きな勇気が要ります。しかし、その一歩を踏み出せたときから状況は少しずつ変わり始めます。話すことで心が軽くなり、具体的な解決策が見えてくることも多いのです。電話の向こうやネットの向こうには、あなたの苦しみに耳を傾け、一緒に道を探そうとしてくれる人がいます。どうか一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみてください。
回復支援施設・リハビリテーションプログラム
日本には、アルコールや薬物依存症向けの回復支援施設(民間のリハビリ施設や施設入所型の更生プログラム)が存在します。その中にはギャンブル依存症の回復支援を行っている施設も少しずつ増えてきています。例えば各地にあるDARC(ダルク:Drug Addiction Rehabilitation Center)は元々薬物依存症者の自立支援施設ですが、近年はギャンブル依存の回復者も受け入れています。また、民間団体が運営する共同生活型のリハビリ施設では、一定期間入所して日常生活の中でギャンブルをしない習慣を身につけるプログラムが提供されます。そこでは当事者同士が寝食を共にしながら規則正しい生活リズムを取り戻し、ミーティングや作業療法を通じて社会復帰を目指します。
公的な入所施設としては、医療機関の依存症治療病棟以外に「地方自治体と民間が連携したモデル施設」も試行されています。例えば横浜市では、依存症者の回復施設利用を支援する取り組みとして、民間の回復施設への入所費用助成やケースワーカーによるフォローアップを行っています。また厚生労働省のモデル事業として、一部地域でギャンブル等依存症の回復施設整備が進められています。
こうした施設に入所するメリットは、生活環境からギャンブルの刺激を遮断できることと、時間をかけて生活習慣や考え方を改める機会が持てることです。同じ屋根の下で似た境遇の仲間と過ごす中で、「賭けずに一日を過ごす」感覚を積み重ね、自信を取り戻していく人も多くいます。ただし入所には本人の強い意志が必要ですし、職や家族から一定期間離れる負担もあります。費用面でも公的補助がない場合は自己負担となるため、利用を検討する際は事前によく情報収集することが大切です。各施設によってプログラム内容や理念も異なりますので、見学や問い合わせを通じて納得できる場所を選ぶとよいでしょう。
回復施設での生活は決して楽なものではありません。時にルールの厳しさや集団生活のストレスを感じるかもしれません。しかし、それもすべて「再び社会に戻ったときにギャンブルに頼らず生きる」ためのリハーサルです。スタッフや仲間の支えを借りつつ困難を乗り越える経験は、大きな自信へとつながります。もし「自分一人の意志ではどうにもならない」と感じているなら、思い切ってこうした環境に飛び込んでみるのも一つの選択です。つらい気持ちを理解し励ましてくれる仲間と共に、更生への一歩を踏み出してみませんか。
海外におけるギャンブル依存症回復支援制度(アメリカ・イギリス・オーストラリアの事例)
次に、海外の主要な国々でどのような回復支援制度が整備されているかを見てみましょう。ギャンブル依存症は世界共通の問題であり、各国で様々な取り組みが進められてきました。ここでは特にアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアの例に注目し、日本との共通点や相違点を比較します。海外の先進事例を知ることで、日本の支援策を客観的に捉え直すヒントが得られるでしょう。また、読者の中には「海外で治療を受けたい」「英語の自助グループに参加してみたい」と考える方もいるかもしれません。そうした場合に役立つ情報も交えつつ、各国の事情を紹介します。
アメリカ合衆国の回復支援:GAの発祥・州ごとのプログラム・NCPGの取り組み
アメリカ合衆国はギャンブル依存症支援の歴史が比較的長く、1950年代に既に自助グループのGAが誕生しています。現在では全米の至る所にGAグループが存在し、日々ミーティングが開かれています。またGAと並んでGam-Anon(ギャマノン)も各地域で活動しており、依存症者本人だけでなく家族もコミュニティで支える土壌ができています。
公的な支援制度としては、アメリカでは各州政府が問題ギャンブル対策を所管しています。多くの州でProblem Gambling Council(問題ギャンブル協議会)や専門の相談窓口が設置され、州予算でホットラインやカウンセリングサービスが提供されています。例えばNCPG(全米問題ギャンブル協議会)は全米統一のヘルプライン電話番号「1-800-522-4700」を運営しており、どの州からかけても自動的に地元の相談機関につながる仕組みになっています。このヘルプラインネットワークには全米で28のコールセンターが参加し、アメリカ領土含め50州すべてをカバーしています。24時間365日いつでも無料で相談できる体制が整っており、電話だけでなくテキストチャットやオンラインチャットにも対応しています。日本でいう「こころの健康相談ダイヤル」のギャンブル版といった位置づけで、誰でも気軽にアクセス可能です。
またアメリカには、民間のリハビリテーション施設も多数存在します。アルコールや薬物依存の治療施設がギャンブル依存症者を受け入れるケースや、ギャンブル専門のリハビリセンターもあります。これらは入院・合宿形式で数週間から数ヶ月の集中的な治療プログラムを行い、心理療法やレクリエーション療法、家族カウンセリングなど包括的に支援します。費用は高額になりがちですが、民間医療保険でカバーされたり州の補助金が出る場合もあります。経済的に困難な人向けには一部施設でスカラーシップ(奨学金)的な減免制度もあります。
アメリカの特徴として、州ごとに制度にばらつきがある点が挙げられます。カジノが合法な州ではその税収の一部を依存症対策に充て、治療費補助や啓発活動に活用しているところもあります。一方でギャンブル産業のない州では公的支援が手薄になりがちで、民間団体のボランティア活動に頼っている地域もあります。このように対応水準に差はあるものの、全体としては「問題ギャンブルは公衆衛生上の課題である」との認識が広がりつつあり、近年は全米規模での予防教育プログラムや研究資金の拡充も進められています。
アメリカから学べるポイント
- 自助グループ(GA)のネットワーク:当事者と家族のグループが全土に広がり、ピアサポートの力が浸透している。日本でもGAやギャマノンをさらに普及させ、地方でも参加しやすい環境づくりが課題。
- 統一ヘルプラインの整備:日本でも都道府県ごとに相談窓口はあるが、全国家庭的な24時間ホットラインは発展途上。アメリカの1-800-GAMBLERのような全国共通ダイヤルは、日本でも参考になるモデル。
- 民間活力の活用:公的支援だけでなく、民間リハビリ施設やNPOの存在が支援層を厚くしている。日本でも民間企業や慈善団体との連携によるリハビリ施設の創設・運営支援など、官民協働の余地がある。
イギリスの回復支援:NHSの専門クリニック・全国ヘルプライン・オンライン支援
イギリス(英国)はギャンブル依存症対策において先進的な取り組みを行っている国の一つです。特徴的なのは、公的医療サービス(NHS)による専門クリニックと、民間団体が連携した全国支援ネットワークの両輪で支援体制を構築している点です。
イギリスでは2019年にロンドンなどにNHS運営の「ギャンブル問題クリニック」が開設されました。このクリニックでは医師やセラピストによる無料の治療プログラム(認知行動療法や家族療法など)が提供され、重度のギャンブル障害患者の治療を専門に扱います。NHS傘下ということもあり費用は原則無料で、かかりつけ医(GP)からの紹介で利用できます。また民間の慈善団体GamCareやGordon Moody協会なども、公的資金の助成を受けながらカウンセリングや住宅型リハビリプログラムを展開しています。
さらに、イギリスには日本にはない全国統一の自己排除制度や広告規制などの施策もありますが、本節では回復「支援」に絞って説明します。支援面で特筆すべきは、ナショナル・ギャンブル・ヘルプラインの存在です。これは英国全土からの電話相談に24時間365日対応する無料窓口で、実際に0808-8020-133に電話するといつでも専門アドバイザーに繋がります。このヘルプラインは慈善団体GamCareが中心となって運営しており、電話だけでなくライブチャットによる相談や、悩みを共有できるオンラインフォーラムまで提供しています。「無料・匿名・24時間」という安心して利用できる環境が整っており、相談者はイギリス国内であればどこからでも支援にアクセス可能です。
またイギリスはオンライン支援が充実している点でも注目されます。先述のGamCareは公式サイト上でチャット相談やメール相談を受け付けているほか、Gambling Therapyという国際オンラインサービスでは英語圏のみならず多言語でのチャットカウンselingを提供しています。コロナ禍において対面の自助グループが開催困難だった時期にも、イギリスではZoomを使ったオンラインGAミーティングなどがいち早く実施されました。地理的な距離や身体的な制約を乗り越えて支援を届ける工夫が進んでいると言えるでしょう。
イギリスから学べるポイント
- 公的医療による無料治療:国営医療サービスNHSが依存症治療に乗り出し、専門クリニックを設立した点は画期的。日本でも国立病院の専門病棟はあるが、より幅広く誰もが無料で専門治療を受けられる環境整備が望まれる。
- 全国ヘルプラインと支援ネットワーク:イギリスのナショナルヘルプラインは無料・24時間で、電話以外のオンラインサポートも充実。日本のサポートコールやRSNも頑張っているが、英国のような統一ブランドでの周知やオンライン相談拡大は検討の価値がある。
- 多様なチャネルでの支援提供:電話、チャット、フォーラム、アプリ(自己管理ツール)など、支援へのアクセス手段が豊富。日本でも若年層にはLINEやチャット相談のニーズが高いはずで、海外の知見を取り入れていくべき。
オーストラリアの回復支援:全国ギャンブルヘルプライン・州ごとの無料カウンセリング
オーストラリアもギャンブル大国ゆえに依存症対策に力を入れている国です。同国では連邦政府と各州政府が協調して問題ギャンブル対策を講じており、特に全国規模のヘルプラインとオンライン支援が整備されている点が特徴です。
オーストラリアにはNational Gambling Helplineに相当するサービスとして、「Gambling Help Online」というプラットフォームがあります。これは電話番号「1800 858 858」で24時間いつでも無料相談を受けられる全国共通ホットラインであり、加えてオンラインチャットやメール相談も同じプラットフォームから提供されています。公式サイトを見ると「Free online support for anyone affected by gambling. Available 24/7 across Australia.(ギャンブルの影響に悩むすべての人に無料オンラインサポートを。オーストラリア全土で24時間365日利用可能)」と明記されており、まさに国を挙げてワンストップ支援窓口を提供していることがわかります。電話でもオンラインでも、経験豊富なカウンセラーが悩みを傾聴し、各州・地域のサポート機関やサービスにつなげてくれます。
また各州ごとにも独自のプログラムが充実しています。例えばビクトリア州では専門クリニックでの無料カウンセリングや自己排除プログラムを実施しており、ニューサウスウェールズ州でも州政府主導で無料のカウンセリングセッション(面接または電話)が一定回数受けられる仕組みがあります。さらに全豪共通で、自己排除制度(希望者がカジノや賭博場への入場禁止措置を取れる制度)やプリペイドカード制度など、依存そのものを予防・管理する施策も導入されていますが、ここでは支援策にフォーカスします。
オーストラリアは地理的に広大なため、遠隔地や少数先住民コミュニティへの対応も課題となってきました。その解決策の一つが前述のオンライン支援であり、さらに多言語対応にも力を入れています。Gambling Help Onlineのサイトは英語以外に中国語やアラビア語など多数の言語に翻訳対応しており、非英語話者でも情報にアクセスしやすく工夫されています。また先住民向けには文化的背景に配慮した専用プログラムやリーフレットを用意するなど、きめ細かい対応が図られています。
オーストラリアから学べるポイント
- 全国共通の無料支援インフラ:フリーダイヤル一本で全国どこからでも24時間相談できる仕組みは、日本の「地域ごと窓口」よりも利便性が高い。日本も全国共通番号の導入や統一的なオンライン相談サイトの構築を検討すべき。
- 州政府の積極的関与:各州が競って依存症対策を強化し、無料カウンセリング枠の提供など具体策を実施している。日本でも都道府県単位での施策推進(例えば地域の専門相談員配置や回復施設支援)が鍵となる。
- 多文化社会への対応:多言語・多文化に対応した情報発信やプログラム提供はオーストラリアならでは。日本でも在日外国人や多様な背景の依存症者に支援が届くよう、言語対応やアプローチ方法の柔軟性が求められる。
国内と海外の支援制度の比較と今後の展望
ここまで、日本国内およびアメリカ・イギリス・オーストラリアの支援策を見てきました。最後に、それらを比較して浮かび上がるポイントと、今後の展望についてまとめます。
まず共通して言えるのは、「ギャンブル依存症は回復できる病気であり、支援を受けることで十分に克服可能だ」という認識です。日本でも海外でも、適切な治療やサポートによって多くの人がギャンブルをやめ社会復帰を果たしています。支援制度の具体的な形態は国によって違いがありますが、根底にある理念は共通しています。
その上で、日本固有の課題としては支援リソースの不足や認知度の低さが挙げられます。例えば自助グループの参加者数は徐々に増えているものの、まだ依存症が疑われる人のごく一部しか利用できていません。GA日本は約200グループと前述しましたが、推計70万人とも言われる国内の問題ギャンブラー人口を考えると十分とは言えません。イギリスやアメリカのように支援ネットワークを広報する国家的キャンペーンや学校教育での啓発が今後必要でしょう。
一方で海外から学べる良い点も既に日本で取り入れられ始めています。例えば電話相談は、イギリスやオーストラリアにならって24時間対応化が進みつつあります(ギャンブル依存症サポートコールは現時点で24時間対応を実現)。オンラインチャット相談も2022年から一部NPOでトライアルが始まりました。また、公的医療と民間団体の連携も強まりつつあり、厚労省委託事業で民間回復施設の活用モデルが検討されるなど動きが出ています。
今後の展望として、日本では2024年度から基本計画(第2期)の下、各自治体で具体的施策が強化される予定です。そこでは「地域の相談支援体制の充実」「医療従事者等の人材育成」「若年層への予防教育」などが重点項目となっています。また、ギャンブル等依存症対策センター(NCASA)をハブとした情報共有や研究推進も期待されています。さらに技術面では、オンライン診療や遠隔カウンセリングを活用して支援アクセスを拡大する取り組みも考えられます。これは地理的・時間的制約を乗り越える上で、イギリスやオーストラリアの事例が大いに参考になるでしょう。
最後に、読者の皆様へのメッセージです。ギャンブル依存症からの回復プログラムは、日本国内外にこれほど多様な選択肢があります。大切なのは、「自分や家族に合った支援を諦めずに探すこと」です。一人で苦しんでいた方も、ぜひ勇気を出して手を伸ばしてみてください。医療の力、仲間の力、カウンセラーの力、そして家族の力――様々なサポートを受け入れることで、回復への道は必ず開けます。ギャンブルに支配されない本来の自分らしい人生を取り戻すために、今日からできる小さな一歩を踏み出しましょう。「今日一日賭けずに過ごす」ことを積み重ね、いつか振り返ったとき「こんなに遠くまで来られた」と実感できる日が必ず訪れます。あなたの回復を心から応援しています。
ギャンブル依存症 回復プログラム理解度チェック
理解度チェック
参考文献
- ギャンブル依存疑い320万人:パチンコ・パチスロに月5.8万円!?(nippon.com)
- ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ(caa.go.jp)
- リカバリーサポート・ネットワーク(RSN)「相互援助グループ」(rsn-sakura.jp)
- 依存症対策全国センター(NCASA)「自助グループのご紹介」(ncasa-japan.jp)
- 国立病院機構 久里浜医療センター「ギャンブル依存治療部門:基本情報」(kurihama.hosp.go.jp)
- Massachusetts Dept. of Public Health – Treatment Recommendations for Gambling Disorders(mass.gov)
- National Council on Problem Gambling – About the National Problem Gambling Helpline(ncpgambling.org)
- Dudley Council, UK – National Gambling Helpline 紹介ページ(dudleysafeandsound.org)
- Gambling Help Online(Australia)– Free 24/7 Support Across Australia(gamblinghelponline.org.au)
- Recovery Support Network(RSN)– GA/Gam-Anon の国内グループ数(2020年2月時点)(rsn-sakura.jp)